有田●そうですね。もっと言えば、構造主義とか言語学とかを含めた彼の知的バックグラウンドも、そのポリフォニーのひとつの線として捉えられる気がする。
沼野●確かに、そうした外に広がっていく部分には、イタリアという国の豊かな文化的背景が作用しているのかもしれません。
有田●やっぱりイタリア人には、ヨーロッパの文化の根本を自分たちのオリジンに持っているという誇りがあるでしょうし。もしかしたらベリオが他の作曲家と大きく隔たるところは、伝統に対する距離かもしれない。ベリオにとっては、伝統は破壊するものではなくて基盤なんじゃないか。常に自分のどこに伝統があるかを意識している感じがするんです。
白石●伝統への信頼というのは、たしかに感じますね。昨年5月の「リンガリング・コンサート」で演奏された《レンダリング》(シューベルト:交響曲10番のスケッチによる)にしても、今回「ベリオ管弦楽作品展」にある《マドリードの夜の帰営ラッパ》やブラームス〜ベリオの《作品120-1》にしても、伝統をまず受け入れるところから発想していますよね。
さっき沼野さんが「注釈」ということばを使っていましたが、1991年にデヴィッド・オズモンド-スミスというベリオの研究者が書いた本の中で、ベリオの注釈技法について1章を割いて論じていて、《セクエンツァ》と《シュマン》の関係について詳しく分析しています(松平頼暁訳『ベリオ―現代音楽の航海者』)。オズモンド-スミスの言っている注釈技法は、すでにできあがった曲について自ら解釈を加えて新しい作品を作る方法を意味しているわけですが、これをベリオのトランスクリプションまで広げて考えてもいいかもしれない。
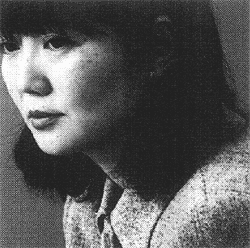
白石美雪 音楽学 Miyuki Shiraishi
ジョン・ケージを出発点に幅広く現代の音楽を研究。『はしめての音楽史』(共著、音楽之友社)、『インターメディアの詩学』(共訳、国書刊行会)など武蔵野美術大学助教授、国立音楽大学講師。
有田●そうですね。結局、トランスクリプションというのは、ブラームスやシューベルトのコンテクストに乗り込んでいって、より深く理解し、解釈し直すこと、書き換えることですから。
沼野●逆説的な表現になりますが、ベリオは「注釈」という行為が実は最もクリエイティブだということを意識しているんじゃないでしようか。だからトランスクリプションといっても、単なるアレンジとは違うんだ、と。

沼野雄司 音楽学 Yuji Numano
東京音楽大学専任講師。現在は1970年の前後の音楽について研究。ベリオやリゲティに関する諭文多数。訳書に、『音楽の新しい地平』(共訳、音楽之友社)ほか。
白石●でも一言で「トランスクリプション」といっても、ベリオの場合、原曲との関係のつけ方、編曲の仕方が随分違うでしょう?
有田●そうですね。今度演奏されるブラームス作品の編曲は、ブラームスの曲の骨組みをほとんど残しています。何気なく聴いていると、原曲よりもブラームスらしかったりして。でも、よく見るとスタイルが全然違うんですよ。なんかだまし絵みたいで、本当に面白い。《レンダリング》もそうですね。あれはシューベルトですが、彼のスケッチを継ぎ接ぎして、その間をまったく新しい音楽でつないでいくんです。最初に聴いた時に思ったのは、スタイルとは何か、っていうことを本当に心得ている人なんだなということ。音楽家としての基本的な訓練が完璧にできてるんですよね、きっと。《マドリードの夜の帰営ラッパ》は、ボッケリーニ自身による4つの異版・異稿を、モンタージュ写真みたいに同時に重ねています。ハーモニーがぶつかりあう効果を狙ったと言っていますが、確信犯ですよね。
白石●マーラーの歌曲の管弦楽伴奏版とか、「イエスタデイ」「ミシェル」の室内楽編曲もある。
有田●モンテヴェルディとか、ヴァイル、ヒンデミットなんていうのもありましたね。こういうヴァラエティを見ると、やっぱり多面体的な人なんだなあと思います。
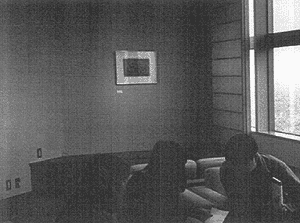
前ページ 目次へ 次ページ