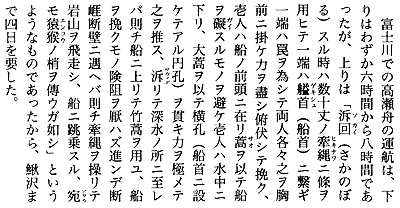
従って、岩淵から鰍沢までの塩の運賃は、塩の代金に瀬戸内の産地から岩淵河岸までの運賃を加算したものより高値であったという。
幕府は、富上川舟運を免許制にし、乗組定数四人、旅客定員十五人と定め、その監視取締りには鰍沢、十島、万沢(十島、万沢は山梨県富沢町地内)に設けた「口留番所」が当たっていた。また、増水時の船留めもこの番所から布告され、事故をおこしたときは、天神ケ滝(鰍沢町箱原地内)までは鰍沢、それより下流は十島の口留番所に注進するように定められていた。明治時代になると警察所轄となるが、十島では必ず舟改めを行い定員については特に厳しかったという。
維新後、富士川舟運は幕府の厳しい規制が解かれて容易に許可が得られるようになり、旧来の三百余艘から一挙に八百艘に膨れあがる。それに連れて、輸送量も江戸時代の塩を見ても、年間十万俵余りが明治になると四十万俵ほど、最盛期の明治三十五年ごろには舟数も千五百艘となった。
一艘に四人の乗り手として就労人員は六千人、この一大産業は流域に大きな経済の波及効果をもたらし、岩淵では船宿七十軒、一カ月の宿泊客は一万五千人余(富士川町史)と殷賑(インシン)を極めた。