思いつくこと
ではどうすればよいのだろうか。これはマスコミ、業界、業界団体が一体となり有効な社会活動を行ってもらい、海事への興味と認識を社会に行き渡らせてもらうほかないように思われる。具体的に思いつくことを述べると……
(1) 業界、業界団体がメディアと好関係をつくり自社の宣伝にとどまらず、海事関連記事を一般紙で取りあげてもらえるように努力する。
(2) 若人を対象とする講演会、寄付講演、乗船体験などを頻繁に行う。特に小中学生を対象にした行事が望ましい(この意味では前述した全国海難防止強調推進大会のあと、八百人の参集者に新鋭巡視船「やしま」で横浜までのショート・クルーズの機会を与えられたのは好適なやりかたであった。予算の関係もあろうがこのような体験航海をもっと頻繁にしてもらえるなら素晴らしいことだ。また日本の客船会社も東京湾〜横浜港、名古屋港〜四日市港、大阪港〜神戸港、門司港〜刈田港などの日帰りできる短区間に限って少年少女を無料乗船させることを考えてほしいものだ)。

人気の体験航海。平成十年は巡視船?やしま?だった
(3) 海事殿堂を造る。博物館など人の集まる建物の一室に日本海事史で功労のある人物や船舶の絵・写真(銅板エッチング)を掲げる。また博物館や海運造船会社が日本海運発展を物語る絵画を制作、展示、貸出できるようにする。
(4) 小中学校教科書に日本の海事史の出来事をテーマにした物語を入れてもらう(岩崎弥太郎や浅野総一郎の物語など感動させるテーマはたくさんある)。…などである。
諸外国の顕彰碑と慰霊碑
「水を飲むときには井戸を掘った人たちのことを思い出そう」とは周恩来首相の言葉と記憶している。国の歴史は人々の行為の連続であることは日本の場合も例外でない。その意味では今日の日本あるは先達の努力や犠牲が礎になっているものと考えている。ここで私が特に言いたいのは戦争などで殉職した人たちの顕彰と慰霊のことである。
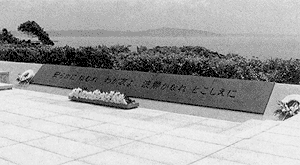
観音崎公園に建立されている戦没船員の碑
オーストラリア西海岸から東岸のシドニーに行くまでの各都市には戦没者の慰霊碑が公園のような場所にちょ立しているのに気づいた。そこにはLet silent contemplation be your offering(静かにしのんで供養しましょう)の文字が必ず刻まれていた。
水と緑で美しいパースの街を見下ろす高台の公園にある慰霊碑にはガリポリ、トブルク、エル・アラメイン、ボルネオ、イプレ、ソンムなど(数多くの豪州兵士が戦没した)第一次、第二次大戦の激戦地の名前とともに殉職者の名前が鮮やかに刻み込まれていた。また公園内にあるユーカリの樹の根もとには戦没者名を記した銘板が取り付けられている。
なお豪州、新西蘭(ニュージーランド)兵士は英連邦国という理由で両大戦ではいち早く戦場に送り込まれ、イギリス軍の拙劣な指揮(ダーダネスル海峡ガリポリ上陸作戦)や敗走(太平洋諸島)により多数の犠牲者を出している。
前ページ 目次へ 次ページ