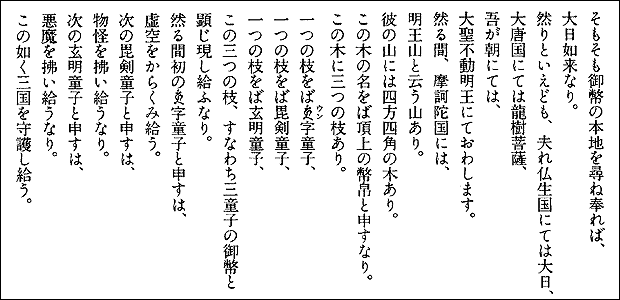御幣の動態学祈祷と祭の現場から……山本ひろ子
はじめに
――天照大神が天石窟に籠ったので、世界は真っ暗闇となってしまった。そこで神々は、天の香具山の榊を根ごと抜き取り、上の枝に八坂瓊(やさかに)の御統(みすまる)を、中の枝には八咫鏡を、下の枝には青和幣(あおにきて)・白和幣(しろにきて)を取り懸けて、共に祈祷した……(『日本書記』本文)。
言わずと知れた、天岩戸神楽の起源神話である。
御幣。幣束。みてぐら。神前に捧げる幣帛の一種で、白・五色・金銀などの紙で作り、竹などの幣串に差した。元は四角形の紙だったが、やがてその両脇に紙垂(しで)をつけるようになり、神霊の依代や祓具として用いられるようになった。繊細な切り紙文化の代表格として、日本各地には多種多様の御幣が存在している。
とはいえ、神社の本殿などにうやうやしく奉安されている御幣を見つめても、神霊の息吹は感じられず、不信心者のわたしを一向に誘惑することもない。
御幣を、お定まりの神の形象や祭場の飾り物から解き放ち、幣帛という古い役割からの変容を見届けるためには、祈祷や祭のただ中で御幣の動態を掬いとる必要がある。そのとき御幣は、とりすました神の依代であることをやめ、思いがけない身じろぎを示すかもしれない。
◎I 御幣の祭文と御幣作り◎
「御幣の祭文」の世界
霜月神楽系の祭が分布する天龍水系の山里。なかでも大神楽(おおかぐら)・花祭の伝承地としてつとに有名な奥三河(愛知県北設楽(きたしたら)郡)は、多くの祭文・詞章を生み出してきた。
そうした祭文群の中には、祭の起源や祭具の出自・聖性を語り、ことほぐものが少なくない。たとえば<花>の宗教義を説く「花の祭文」や、釜の神の由来と禁忌を説く「釜の神の祭文」などである。
とすれば、神の依代である御幣の聖なる本地を語り、讃えた祭文が存在してもよいだろう。事実、豊根村(とよねむら)の禰宜屋敷には、「御幣の祭文」(注1])(仮称)と呼ぶにふさわしい祭文が伝わっている。