81. 生活状態を改善するには、以下の三つの基本ステップがある。
□ 人口過密や人口過剰を避ける。このような状態では、ノミやシラミなどの病原体媒介生物によってもたらされる病気の(直接・間接接触による)伝染が増える。
□ 調理や食事の前に必ず手を洗わせ、糞便/経口感染のリスクを減らす。
□ シャワーや洗濯場・たらいなどを支給し、清潔な衣服など個人の衛生を促進する。これにより排泄物で汚染された水との接触も減り、ビルハルツ住血吸虫症(schistosomiasis)などの病気にかかる危険も減る。
◆死体の処理
◆ 死体処理については、緊急事態の最初から適切な手配が必要である。
◆ 国の関係当局と調整して対応する。
◆ 許容され物理的にも可能なら、土葬が一番簡単で優れた処理方法だ。伝統的な葬式がコミュニティわれるよう手配する。
◆ 土葬または火葬の前に、死体の身元確認して記録を作成する。
82. 死体処理については、難民緊急事態の最初から適切な手配が必要となる。死亡率が、「平常」時よりはるかに高い場合もある。国内の手続きを守り、必要なら支援を受けられるように、当初から関係当局と連絡を取り合う。
83. 死体(dead bodies)は、死亡原因が発疹チフス、ペスト(感染したシラミやノミが寄生している場合)、コレラでない限り、健康に深刻な危険を及ぼすものではない。コレラによる死者の葬儀は、死亡場所の近くで速やかに行なう。上記3種類の病気が原因で死者が出た場合は必ず葬儀参列者を制限する。徹底的な保健教育、または適切なら立法措置を取って、葬儀後の食事のふるまいや死体を洗う清めの儀式を制限する。
84. 十分な燃料が手に入らない場合も多く、保健衛生上の理由から火葬を正当化する理由はない。なるべく慣例に従った死体処理法を取り、伝統的な習慣や儀式を認める。埋葬布などの物的ニーズに対応し、埋葬に必要なスペースは、特に人口が多い場合、用地計画の段階で考慮する必要がある。
85. 土葬または火葬の前に、死体の身元を確認して記録する。病気の防除、登録、追跡調査に際して特に重要となるので、できれば死亡原因も記録する。親類の居場所が分かる場合は、一番の近親者に連絡する。また、死亡によって成人の保護者を失った未成年者がいる場合は、そのケアを確保する措置をとる。
86. 死体を運ぶ時、作業者は手袋、マスク、長靴、オーバーオールなどを着用する。作業後は、石けんと水で十分に洗うこと。HIVウイルスは死体の中では長く生存できないが、体液には注意が必要である。
主な参考文献
A Guide to the Development of On-Site Sanitation, WHO, Geneva, 1992.
Chemical Methods for the Control of Arthropod Vectors and Pests of Public Health Importance, WHO, Geneva, 5th edition 1997.
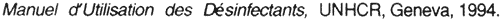
Sanitation and Disease: Health Aspects of Excretia and Wastewater Management, Feachem & al, Wiley & Sons, 1983.
Vector and Pest Control in Refugee Situations , PTSS, UNHCR, Geneva, 1997.フランス語版もあり。
Vector Control: Methods for Use by Individuals and Communities, WHO, Geneva, 1997.