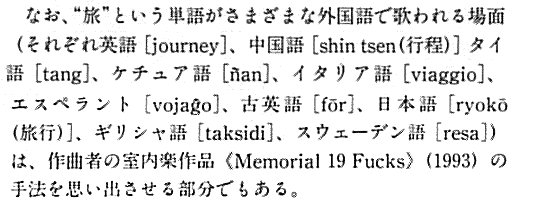梗概
マルコ・ポーロが自らの中国への大旅行を記した「東方見聞録」は、中世ヨーロッパ世界に東洋世界のさまざまな情報をもたらして人々に新鮮な衝撃を与えた書物である。しかしその一方では、当時のヨーロッパ人には奇想天外な物語としか思えないその内容のため、この書に描かれた内容は、マルコ・ポーロの単なる空想の産物ではないか、との臆測もなされていた。事実、中国への旅が著されているにもかかわらず、“万里の長城”については一言も言及されていない。
果たして「東方見聞録」に描かれた大旅行は歴史上の事実であったのか。また空想の物語であるならば、その旅行譚が意味するものは何か。
多くの謎とともに、マルコ・ポーロの「時空之書」が開巻する…
【時空之書:冬】
「私はまだ、見たものの半分も語っていない(I have not told one half of what l saw)」――闇の中、マルコ・ポーロが晩年に語った言葉からこの“劇中劇”は始まる。“記憶の声”であるポーロと“現実の存在”であるマルコに分断された主人公。このふたつの存在に語り部としての影、ルスティケッロ(「東方見聞録」の口述筆記を手がけた物語作家)が語りかける:「吾と来たれ … 汝、吾を伴いて(Come with me … Take me with you …)」
「それは、まさに先の如く?(Will it be like last time?)」「否!(No!)」
影はマルコ・ポーロに、精神の彼方に向かう新たな旅の開始を呼びかける。
打楽器群が京劇を想わせる音楽を響かせてこの物語を開始する。マルコ&ポーロ、ルスティケッロなど独唱者たちの音高不確定な朗唱(譚盾の愛好する声楽書法のひとつで、《オン・タオイズム》(1985)《九歌》(1989)などの作品に大々的に用いられている)や、自由な装飾を施した弦楽器のボルタメントなども同じく中国の伝統戯曲音楽を想わせるが、同時に精神の深奥で展開する不定形のドラマの萌芽をも予感させる。
マルコ&ポーロは、一文を単語に分割しながら歌い始めるが、その後このふたつの存在が、接近し合一に至るまでの間、次第に二重唱の形を呈するようになる点に注目すべきだろう。
◆広場
旅はマルコ・ポーロの故郷ヴェネツィアの広場から始まる。
彼方の闇から「行け … 来たれ … (Go … Come …)」という声が響き、森のように暗い、憂鬱な迷宮としての街の姿が浮かび上がる。もう一人の語り部である影のダンテがこの場面を紹介する。「到来 … 旅立ち … (Coming … Going …)」と、聖歌風の合唱がマルコ・ポーロの旅立ちを促し、“記憶の声”ポーロは「ヴェネツィア――風が広場を吹き抜ける。唸り声を超えて、指先ほどの近さを超えて … (Venezia――vento attraverso la piazza …)」と、風に託して旅立ちへの想いを歌う。「急ぎ行き、旅のただ中に加わらん!(Go,hurry,join into journey!)」――さまざまな言語で“旅”が語られたのち、合唱がポーロの新たな世界に向かう旅立ちを力強く促す。
ポーロと同様に、旅立ちの時を待つ存在が登場。遥か中国は大モンゴル帝国の皇帝、フビライ・ハーンである。彼は舞台から離れた場所で、やはり風に託して自己の内面への旅、“フビライ・ハーンになるための”旅を待ち続けている、と歌う。
あたかも出生の瞬間を描くかのような緊張感ののち、「過去は往き続け、未来は現在に先立つ。すべての時は記憶の中に織り込まれる(The past goes on …)」と歌う合唱とともに闇の世界は光に向かって解き放たれる。新たな世界への旅が始まったのである。広場に響く聖歌を記憶の彼方に残しつつ――
この情景では、全曲を通じて重要な意味を担うモティーフがいくつか登場する。
まずオーケストラの発声する「否(no)」とともに低弦に現れるモティーフ(e-d-c-a-d-e)は、この歌劇の中心モットーともいえるもので、「地域の旅」の中に音程やリズムなどの変容をなしつつしばしば登場する。就中〈広場〉〈長城〉〈同(続)〉で現れる、此岸と彼岸を隔てる堅牢不落の壁(=長城)を想起させるコラール風音型は重要なテーマのひとつである。
続いてダンテ「何という場所だ(What a place that was)」の背後で聞かれるオーボエのモティーフは、“未知への旅路”を手探りしつつ進む探究者のイメージを喚起させる。
ポーロによって歌われるアリアは、〈広場〉〈砂漠〉〈長城(続)〉の各情景に現われ、それぞれイタリア語、無言、中国語と異なる言語の衣装を纏いつつ“旅への憧憬”が歌い上げられる。またこの旋律は異なる基音と若干の変形を経て合唱に受け継がれている(〈広場〉の「過去は往き続け」、及び〈長城〉の「石、歌」など)。