米国
受け入れることができる代替メカニズム
−
米国は、バラスト水管理への広範囲な免除措置が不在であることを思慮しながらも、関連規則が、新技術の開発を奨励する柔軟性のある骨組みを提供する必要性を確信している。目標は、規定の標準又は基準に従った新バラスト水管理方策の実験及び適用を見込んだ規定を通じて達成できるのではないか。このような規定は関連規則に最大限応じたもの、かつ、海洋性生物の移動問題を処理する効果的管理法策の開発及び実施を促進するものでなければならない。また、元来の船舶運航及びスケジュールの崩壊を最小限にするものでなければならない。
現時点においては、バラスト水交換が、船舶に適用できる唯一の実行可能なバラスト水管理方策である。ガイドライン及び規則案は、深海航海時のみにバラスト水交換を要求すると共に、バラスト水交換が安全に実施できない状況下に対する必要な免除措置を規定しているので、船舶は、航海中100%バラスト水交換を実施しないであろうことを理解している。それゆえ、バラスト水交換を、海洋性生物拡散問題のための唯一の暫定的対応策とみなすべきである。それゆえ、新条約は、新しくかつ安全な、より効果的バラスト水管理技術の開発を奨励するものでなくてはならない。
現規則案は、新たに出現したバラスト水処理方策を編入するための検討及び改正について規定している。様々なバラスト水処理方策を実験する研究・開発プログラムが進行中で、関連データを分析中である。しかしながら、規則案は、これらの方策が本船実験されること及びバラスト水交換と比較して評価されることについての規定を含んでいない。
最も効果的な国際環境議定書のいくつかは、技術革新を促進するインセンティブ
プログラムを通じて汚染防止を助長するものとなっている。新しくかつ安全な、より効果的バラスト水管理技術の開発を奨励するためには、規則のなかに、新たに開発中のバラスト水管理方策の実験及び適用のための規定を加えることを勧告する。
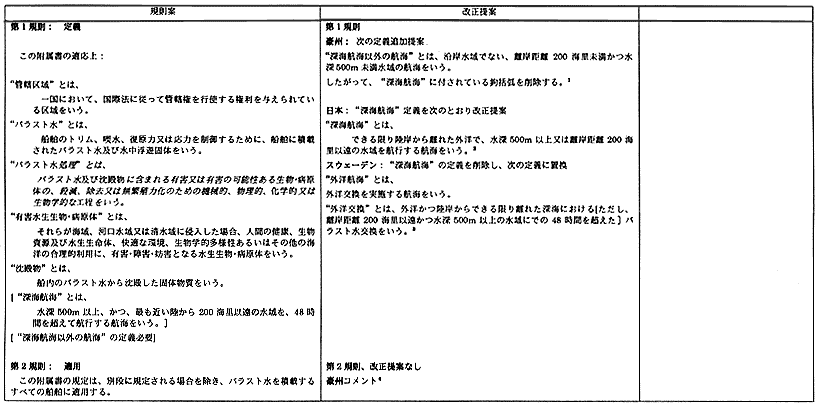
| 1 |
"深海航海"とは、48時間を超えて、水深500m以上かつ離岸距離200海里以遠の水域を航行する航海と定義されている。このことは、多くの国及び航海にとって実施を不可能とするものである。豪州の場合、大部分の船舶は東南及び西南アジアから豪州諸港に入港するもので、付録1、バラスト水管理コード、Part
A、第1節に記載のバラスト水管理選択肢の一つを実施するのに十分な水深・時間を得られる水域を航海しない。
|
| 2 |
日本/豪州、日本/シンガポール等の長期間航海においてさえも、48時間を超えて離岸距離200海里以上の水域を航行することはない。 |
| 3 |
スウェーデンは、ガイドライン(A.868(20),第9..2.1項)の表現"できる限り陸岸から離れて"を結合して含むことを提案する。このような変更は、次の規則のさらなる変更を必要とすることになる。4.1(a)及び4.4規則;コード、Part
A、第1節A1,A3,A4項及び第3節A項 |