絵で見る日本船史
射水丸(いみずまる)
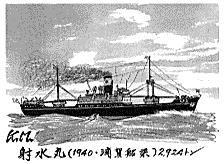
昭和14年12月29日に、政府主導で北日本汽船、大連汽船、朝鮮郵船の3社合弁の国策会社・日本海汽船が創立され、翌年2月11日に各社の現物出資船、6、4隻を夫々提供し11隻で営業を開始、新潟、伏木、敦賀を起点に清津、羅津、雄基への北鮮航路及び敦賀・浦塩航路を開設した。
開業2ヶ月余の4月26日に北日本汽船の射水丸が浦賀船渠で竣工、直ちに日本海汽船の船列に参加し創業後初の新造船として、翌5月に伏木港を出帆、7尾経由で清津向け処女航海に就航した。
日本海富山湾伏木港と北鮮を結ぶこの船には、高岡古城址に鎮座する由緒ある旧国弊中社射水神社に因んで、射水丸と命名された。
総屯数2,924屯の中型貨客船で主機は浦賀式複2連成低圧タービン連動汽機、出力2千百馬力で最高速力15.1節、全長93米、幅13.7、深7.5、船客定員、1等12名、2等30、3等536、計578名の設備の船である。
船体構造は浦賀式縦横肋骨方式最初の採用船で、後年第1次戦標B型に採用された標準船であった。
新鋭貨客船射水丸の就航は開業3ヶ月後で、当時日本海横断航路には大型の月山丸と満州丸が新潟を起点に北鮮航路に就航、気比丸、はるぴん丸、さいべりあ丸の3隻が敦賀から北鮮と浦塩航路に従事し各線月3回定期を実施していた。
伏木起点で七尾経由の北鮮航路には中型の北鮮丸が月2回就航していたが、毎航貨物、船客兵満杯状態が続き、射水丸の役人は時宜にかなった就航であった。
昭和14年4月政府指導のもと標準船型の研究が進められ、その結果標準型貨物船ABCDEF型6種の決定を見て、射水丸は平時標準船C型第1船として翌15年4月に完成、第2船は姉妹船白海丸で進水は射水丸より40日遅いが船型は海軍の要請で砕氷船に変更され射水丸より3ヶ月早く竣工、北日本汽船の樺太西岸に就航した。
射水丸を1番船として建造した浦賀船渠では標準同型の貨客船、貨物船、改造型油槽船等計8隻を竣工し、他造船所では鶴見造船が7隻、日立造船が9隻、三菱神戸6隻、三菱横浜4隻、播磨造船が2隻で合計36隻竣工したが、後年太平洋戦争中には戦時標準船C型として建造されたのである。
好況の日本海航路に就航の射水丸は、僅か半年余りの活躍後の同年12月3日に海軍徴傭船となり、舞鶴鎮守府所属の特設運送船として直ちに改装工事が施工された。
翌16年1月15日連合艦隊付となり、佐世保を母港として中支方面に出動し軍用物資の輸送や、将兵軍属の移送任務に従事した。
太平洋戦争開戦直前には、内地と台湾馬公基地を往復、開戦時の比島各地進攻作戦の海軍支援部隊向け補給に当り、翌17年半ばには大湊基地に転属となり、アッツ、キスカ島占領直後の北洋方面輸送に活躍、年末には横須賀を母港に近海各地への輸送に活躍した。
昭和18年5月末には占領後僅か1年のアッツ島が玉砕の悲運となり、7月末のキスカ島撤収成功の後は、再び北洋に転じて千島、樺太、北海道方面で年末まで活躍したが翌19年初頭、米軍の反撃が日々激烈となった南太平洋方面に出動を命ぜられ、救援作戦の為トラック、グアム、サイパン基地や、小笠原の父島等へ出撃した。
昭和19年6月11日米軍機動部隊接近の報により、サイパン島撤収最後の船団に加わり、同未明に出港、浜江丸、天竜川丸など計32隻と共にに北上中、翌12日0930マリアナ諸島アラマガン島西200浬で、米軍艦載機の熾烈な反復空襲を受けて、船団は支離滅裂、大半が沈没し建造後僅か4年の射水丸は悪戦苦闘の末沈没、乗組員、船砲隊員犠牲者64名を道連れに南浜深く消え去った。
松井 邦夫 (関東マリンサービス(株)相談役)