なお、法定による救命胴衣の備え付け義務のある船でも、これが着にくいなら別の着やすい救命衣を購入、常時着用して、事故が発生し時間的余裕のある場合には法定の救命胴衣を着用するという考えに割り切ることが必要と考えます。
(余談)救命衣をより安価にし、Jリーグのようなカッコよさも加えるためには、漁船、漁具メーカー等の広告ロゴマーク、イラスト等を宣伝費をいただいて表記するのもよいと救命胴衣メーカーに話しましたが、観客のいない海上なのでそのような広告料は期待できないとのことで、この話はチョン。
沿岸海域の事故は早期捜索可能
沿岸海域操業漁船からの海中転落事故では、目撃者があったり無人の船に気が付いたりして、当日明るいうちに捜索されればよいのですが、多くの場合は夕方の入港時間になっても帰港しないとして、家族や僚船から連絡があり、捜索が開始されることとなります。
もちろん浮いていれば夜間の捜索での発見も可能ですが、なかなか発見が困難ですので、翌朝になっても“浮いてさえいれば”発見される可能性が大きいということはお分かりになると思います。
また、沿岸部であるので漁協や海上保安庁による捜索も早期に現場付近に到着して開始されます。
航空機による捜索も早くから開始されます。
これらのことから、とにかくこの間浮いていれば発見・救助される可能性が非常に高いといえましょう。
なお、映画「タイタニック」のように海水温度が低い海に投げ出された場合には、体温が奪われることにより生存時間が制限されますが。失礼を省みず申し上げますと、このような不幸な事態になった場合でも、救命衣を着けていれば発見が早く、僚船等の長期捜索の必要はなくなると思います。
常時着用の運動の全国展開
港湾内での荷役作業とか岸壁、防波堤、橋梁建設等の海上工事に従事している作業員は、全員常時安全作業衣を着用しています。
法的に裏付けされていることもありましょうが、会社等の組織としての事故防止意識、現場各人の共通認識が行き渡り、当然のこととして乗船前に皆が「さあ着よう」という常識として身についたものになっています。
単独行動で個人の意識の強い「私は大丈夫」という沿岸漁業者には、全国規模または県全体、漁協全体での取り組み、“妻と子にチョッキ姿で見送られ”などのように奥さん等家族も巻き込んだ「皆んなが着るんだ俺も着る」というような運動展開(外力)による雰囲気、意識作りが絶対に必要だと思います。
組合員の順守事項規定を作り、また共同購入、若干の補助を行う等いろいろな取り組み方をして成果を上げている漁協もありますので、これをモデルとして積極的に取り組んでいただきたいと思っています。
このキャンペーンを関係機関、漁船、漁具メーカー等と連携をとり、協力を得て展開し、着やすく、着たくなるような(漁協がまとめて多く注文し、漁協のカツコいいネーム、ロゴマークを付けるなど)、そして安価なものを開発することが、普及と量産(低価格)双方においての相乗効果をもたらすことになると思います。
私もそのための努力を惜しまない所存です。
“あっ・ドボン着てて助かるベストワン”
〔参考〕
浮いても船に上がれないとのこと。このようなロープを垂らすだけでOKです。
図 船に這い上がれるロープ
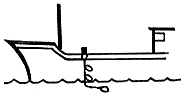
漁場デロープを垂らす
3つの輪を作る(足掛け)