船橋内はいずれも左右のウイングがあり、ウイングにおいても操船シミュレーターの機能をフルに使用できるようになっている。ジョイスティック操船装置やVTS機能はなく、比較的新しい機器としてDGPSがあった。
操船シミュレーターコースは4人の受講生が対象で2週間にわたって行われていた。はじめの日は講義があり、2つのシミュレーターを訓練に応じて使い分け、1日6〜7回のシミュレーションが行われていた。
受講生は船会社からの派遣で、若い2等航海士と3等航海士であった。船長担当、レーダー担当、舵担当、テレグラフ担当を順番に交替していた。訓練を実施する側は1人の教官と1人の電子技師の2人ですべてをこなし、訓練を30〜40有している。
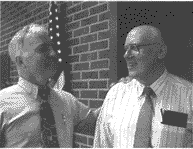
MITAGSの教官
ここでの訓練の方法は初め簡単な講義によって基本的な操船に関することを教えた後、シミュレーター機器の習熟訓練をして、後はやさしい訓練から徐々に難しい訓練へとステップアップしながら訓練を繰り返すやり方である。
筆者が見た訓練は、約15分の事前指示、約1時間の訓練、15分の体験報告の繰り返しであった。すべて熟練の船長、パイロット経験者であり、彼らのライセンスの写しが額に入れ示されていた。
訓練の最中に「それでよいのか」「このようにすべきだ」と別室のコントロールセンターからどんどん指示を出し、体験報告の際にXYの座標に描かれたデータをもとに教官が評価していた。
受講生は訓練の終わるごとに教官を囲んで「これでよかったのか」「あのとき、どうずればよかったのか」等と信頼する大先輩に対する態度で具体的な質問をしていた。
ベテランの教官は後輩に答える態度で逐一応答し、その訓練が標準以下の結果であった場合は、少し訓練の内容を変えてシミュレーションを繰り返していた。
及第点に達した受講生は、教官のサインつきXY座標記録を嬉しそうに貰っていた。
ここでは操船シミュレーターという呼び名の示すとおり、船橋共同操船を訓練するというよりはチームで行う操船そのものを経験者が教えるという比較的単純明解な訓練風景を見た。

世界一を誇る船橋シミュレーター
昼夜兼用の操船シミュレーターでは、2万?のコンテナ船を自船として、離岸した後湾曲した幅250?の狭い航路に出て、そこで他船と行き会うという訓練が、狭い水路を他船と行き会った後、大きく曲がって着岸するというように同じ場所で6〜7回繰り返されており、他船と接触するという場面もあった。夜間専用の操船シミュレーターでは、同じ問題を航路ブイと、反航他船だけで船橋が大きくピッチング、ローリングする中で行われていた。
昼夜兼用シミュレーターも夜間専用シミュレーターも夜間であればほぼおなじであるが、夜間専用シミュッレ一夕ーはコンピュータグラフィックでないのでリアル感があり、その分、受講生も頑張っていたようだ。