海の気象
台風に関する
最近の話題
おかむら
ひろふみ
岡 村 博 文
(気象台予報部太平洋台風センター予報官)
はじめに
11月を迎えると、日本列島に直接影響を及ぼす台風はほぼなくなります。しかし、台風の発生がなくなるわけではなく、多くの船舶が行き交う北西太平洋では、これからも引きつづき翌年の1月ごろまで台風の影響がありますので油断できません。
ここで、台風に関する最近の話題を2つ説明します。
最初に、今年の台風1号の発生が遅れた理由を説明します。今年の台風を振り返ると、第1号の発生が遅れるとか、その活動が前半から、極めて弱いということで、マスコミの注目を浴びました。エルニーニョの動向から、台風発生の遅れをどれだけ説明できるのでしょうか。
次に、別の話題ですが、台風予報精度についてお知らせいたします。気象庁では、昨年から72時間先までの台風の進路予報をしています。予報精度を考慮して、船舶の安全運航に役立ててくださるようにお願いします。
今年の台風発生の遅れ
今年の台風第1号が発生したのは7月9日で、これまで最も発生が遅かった7月2日(1973年)の記録を更新しました。
昨年の11月を最盛期とするエルニーニョの影響で、フィリピン東方海上の海面水温は、年平年値を下回る状況が続きました。それでも4月以降になると、海面水温も摂氏28度程度にまで上昇しています(図1)。台風にエネルギーを供給しているのは、雲や雨のもとになる水蒸気です。海面水温が上がると、海から大気中に供給される水蒸気の量は急激に増加します。そして28度の海面水温は、台風の発生には十分な条件です。今年の5月ごろ、エルニーニョの終えんと同期するように、熱帯中部太平洋から西側の海域の対流圏下層で貿易風(東風)が、一様に強く吹き始めました。それまでは、一貫して東風が弱いのか、逆の西風すら吹いていたのですから、このとき大気の側に劇的な変化が起きたのです。これに対応して北西太平洋の高気圧が、例年より南に偏って勢力を強めました。高気圧の圏内にある海域では、台風の発生は困難です。しかもフィリピン付近の対流圏上層では、下層と逆向きの西風が吹いており、これも台風の発生をさまたげていました。
図1 北太平洋の月平均海面水温(1998年4月)
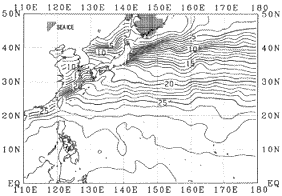
例年、熱帯の海上では、夏半球の貿易風と冬半球側から赤道を越えてくる貿易風とが合流する所に、熱帯収束帯ができます。これは、気象衛星では夏半球の熱帯海域で東西に、長く伸びる雲の帯として見られます。この収束帯の中で、台風がよく発生します。しかし、今年の台風シーズンの前半、北半球側の熱帯海域は高気圧に覆われたため、5月を過ぎても北半球の熱帯収束帯の活動は弱いままでした。それだけでなく、南の冬半球側に、顕著な熱帯収束帯が持続しました。これは北半球の強すぎる貿易風が赤道を越えて、南半球にまで及んだ結果です。