ワイヤの間を通り抜けながら慎重に作業を続けているうちに、ふとしたはずみに身体の安定をくずし、艙口蓋の下に落ちた。
落ちるとき、締付用金具の角ばったところで右足の向こう脛をしたたかに打った。激しい痛みがはしった。私の近くで同じ作業をしていた同僚の北川と村上がこの異変に気づいて「大丈夫か?」と声をかげながら私のところにおりてきた。激しい痛みに耐えているだけで状態がどうなのか暗くてよく見えない。
2人に、両側を支えられて薬品のおいてある部屋へ運ばれた。打撲個所は裂けて出血がなかなか止まらない。急きょ駆けつけて来た3等航海士により傷はきれいに消准され、薬を塗布して包帯された。それからはむっとする船室で汗をふきながら、痛みに耐えなければならない時間が続いた。
翌20日になり、狭い船艙で不自由な生活をしていた部隊の人たちは次々と下航していった。船では、昼は太陽の照りつける強い日差しの中を揚荷役作業に大わらわ。さらに徹夜へと労務が続き、3月22日早朝に陸揚げ作業が終ってまもなくグァム島を出港。同日夜、サイパン島に到着。
グァム島を出港するころ私の足ははれがひどくなり、ひたすらむくみと痛みに耐えていた。サイパン島へ着くなりすぐに病院に行った。テント張りの野戦病院で軍医が診察した。化のうしているが切開するにはまだ早いと言われ、薬の塗布と包帯の交換を受けて帰船した。
南洋群島周辺の戦況はすこぶる悪い。連合軍の反攻により日本軍は次々と島を奪われていった。サイパン島からも民間人が本土へ引き揚げていった。
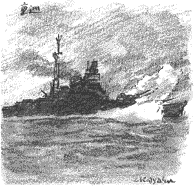
3月24日朝、玉鉾丸はサイパン島から内地へ引き揚げる民間人約300人を乗せて復航の途についた。往航と違って14隻の輸送船団が7隻の海軍艦艇に守られての航海である。サイパン島を出てからというもの、ふたたび敵潜水艦に対する警戒の厳しい毎日をすごした。
私の足の傷はかなり化のうしていて歩行に不自由した。便乗者の中にサイパン島で看護婦をしていた人がいて、毎日傷の手当てをしてもらっているうちに少しづつ回復してきた。
4月1日、玉鉾丸は戦々きょうきょうつづきの航海を経て、無事東京港に入港した。翌2日、私は傷病下船する羽目になった。その後すぐ玉鉾丸は再び将兵の輸送任務で南方に向かった。
昭和19年6月3日シンガポール港を出て門司港へ帰路についた玉鉾丸は、入港を翌日にひかえた6月24日午後11時54分ころ、長崎県野母崎から南西方約20??付近で敵と遭遇。敵潜水艦タングの猛攻撃を受けて沈没、船員33人が戦死した。戦死者名簿の中には私と交代で乗航した河村の名前があった。
玉鉾丸遭難からすでに半世紀を越えた。もしあの時、私が負傷しないで乗船を続けていたら、まちがいなく戦死している。そう思うと、人の運命の巡りあわせの不思議さを覚える。
長い歳月を経過した現在、時折乗航することもあるが、向こう脛にとどめている傷あとを見ると、戦時中の不幸と幸運がよみがえってくる。河付を思い出し、心の中で手を合わせる。