 22
22
向こう脛の傷あと
山本 繁夫
岡安 孝男画
私の右足の向こう脛に長さ約7センチメートル、幅2センチメートルほどの傷あとが残っている。半世紀以上も前に受けたもので、この傷のおかげで危うく難をのがれ、現在の私がいる。そういう受難と幸運を意識させられる昨今である。
太平洋戦争は起動部隊の真珠湾奇襲によって、昭和16年12月8日米国の太平洋艦隊の主力撃破という戦果で幕をあけた。
翌17年7月、ツラギ・ガダルカナル島に上陸。反攻が開始された。翌18年2月ガダルカナル島の日本軍は撤退し、5月にはアッツ島の日本軍守備隊が玉砕した。
翌19年に入り、1月に連合軍がマーシャル諸島へ進攻を開始。2月にはクェゼリン島、ルオット島の日本軍守備隊が玉砕した。米国の機動部隊によるトラック諸島の大空襲など、次第に日本の旗色は悪くなっていった。大本営は、反攻を開始してきた連合軍に対して、南の島々の防備を強化するため、対ソ連戦に備えて満州北部に配備していた関東軍を転進させることになった。
当時私は玉鉾丸(6,700総トン)という陸軍御用船に乗り組んでいた。19年3月に入って早々、満州北部から南下してきた関東軍の将兵2、000人と部隊の隊属貨物を釜山港で積み、3日に同港を出港、3月8日横浜港外に到着、新たに編成された船団にくりこまれた。
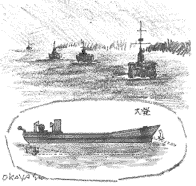
東松輸送二号船団、陸軍御用船6隻、海軍御用船6隻、一等巡洋艦龍田を旗艦とする海軍の艦艇9隻に護衛され、3月12日早朝集合地の木更津沖を出発し、船団はとりあえずサイパン島方面に向かった。
東京湾を出た船団12隻は、翌3月13日早朝、八丈島の南西方約40キロメートル付近で敵艦に遭遇、護衛旗艦の龍田と海軍御用船の国陽丸は米国潜水艦サンドランスの魚雷攻撃を受けて沈没した。その後、敵潜水艦出没の情報がひん繁に入って緊張の航海が続いた。玉鉾丸はサイパン島で他の船と別れ、3月19日無事グアム島についた。
入港しても、いつやって来るかもわからない空からの敵襲を気にしながらの揚荷役作業である。さっそく第2船舶の上に積んである大発(大発動艇、兵員80人を積んで揚陸作業に使う舟艇)4隻を揚げる準備にかかった。
甲板上に積んでいるので、航海中に遭遇する荒天による固定のゆるみなど危険な場合を考慮して、かなり厳重に固縛してある。そのために解く作業にも時間がかかる。夜になっていくつかのカーゴライト(荷役灯)が点灯されていたが、大発の間は狭く十分に照明が行き届かない。縦横や斜めに取り付けられたワイヤの間をくぐりながらの作業は思うようにはかどらない。ワイヤの端をとめてある締付用金具のネジをゆるめて外す。足場が悪く身体が不安定になりやすいので、油断しているとすべり落ちるおそれがあった。
夜になって風もなく全身汗だくだった。