ひかり
若山牧水と灯台
社団法人 燈光会
神子元島灯台
神子元(みこもと)島は、伊豆半島の南端の下田港からさらに南に10キロ?沖合にある周囲2キロ?高さ32?の岩島で赤焼けた火山円礫岩と凝灰質角礫岩からなる一木一草もない無人の小島である。
この灯台は、開国の歴史を飾る慶応2年にアメリカ、イギリス、フランス、オランダの4ヶ国と結んだ「江戸条約」によって建設を約束せれた8つの灯台の1つ。いわゆる「ロックアイランド」として指定された島の灯台である。
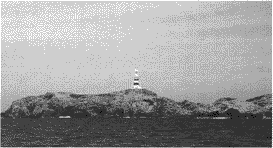
神子元島灯台
英国人技師R・H・ブラントンにより建設された。灯塔の築造には地元の伊豆石を石の上下左右の継ぎ目にはこれも地元産出の火山灰と石灰岩で速成のセメントを用いた。
この石造り灯台はわが国に現存する最古のもので後年の関東大震災にも少しの被害も受けず、石造りの宿舎、倉庫共々建設当時の姿をとどめており、昭和44年7月に国の史跡に指定されている。
明治2年1月に着工、3年11月11日完工点灯した。点灯の前日には太政大臣三条実美、参議大隅重信、大久保利通、英国公使ハリス・S・パークス、同領事アーネスト・サトウ、そのほか朝野の貴顕が品川から灯台用船テーボール号に乗船し、翌11日に神子元島に到着、ブラントンの案内で灯台点灯式に出席した。「これ顕官臨場のはじめとす」と史書にある。
明治初年に建設した灯台の看守には、スコットランドの熟練した灯台員を主員として、その下に日本人助手がついて業務の苦得に勤めていたが、神子元島は明治9年まで続き1番遅くまで残っていた灯台。現在80万カンデラの光を放ち、光達距離は、19・5カイリとなっている。
灯台余話
神子元烏は、釣り場としても有名な島であるが、この島にまつわるいくつかの逸話がある。
(その1)神子元島灯台賛歌
まず1番に知ってほしい話として、この灯台について作家の石原慎太郎先生が、「岬と燈台」(暁教育図井出版)に青柚されている、部を引用して紹介したい..「疲労と迷いと恐怖の中で1点、探し求めて来た燈台の灯をついに認めた時の、あのしみじみした安らぎと充足と歓喜を……
その灯は、燈台のある烏や岬を明かすだけではなく、私たちの船のあるところを示しているだけではなく、海の上でしか自らを充たすことの出来ぬ私たちの心の内、その生きざまを照らし出してくれるような気がしてならない。……」
燈台だけが海と陸という本質的に全く異なるものを、海行く私たちのためにつなげてくれる。
(その2)神子元島灯台と若山牧水歌碑
旅を愛し、また酒を愛すること深く最も歌人らしい歌人として広く親しまれた若山牧水先生は、28歳の秋、東京・.零岸烏から汽船で伊豆の、下田に渡り、下田から1週間おきに神子元島灯台に勤務する職員の飲料水、米、味噌等の生活必需品を運搬する船に乗って神子元島に渡った。
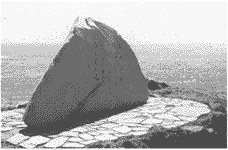
下田市に建立された若山牧水の歌碑