★ 海上浮標式の水源を間違えたばかりに乗揚げ
3月のある日199総トンの貨物船が、夕方大阪港を出港し兵庫県の日本海の港へ向かった。船長のBは日本海を航行した経験がなかったので、最初、日本海西部では沖合を航行することにしていたが、以前、海士(アマ)ケ瀬戸を通航したことがある父から「本船でも通航はできる」と聞いていたので、そこが昼間であればこの瀬戸を通航しようと、備付けの海図201「倉良瀬戸至角島」(縮尺8万分の1)をあたれば何とか通航できると思っていた。
この場合「何とか通航できる」のではなく、発航前にこの瀬戸付近の人縮尺海図115(縮尺3、5万分の1)を始め、関係水路図応を備付け水路調査を十分行っておくべきであった。
さて、海士ケ瀬戸は図3に示すとおり角島東岸と本州の間の「海士ケ瀬戸」の浅所を南北に切り開いた巾約50?、水深3.1?の掘り、下げ水路で、専ら、200トン以.上の船舶が通航する狭い水道で、その東側にこの瀬戸の南口(海上浮標式の水源は港湾をはじめ特定の水源が指定されている海域以外は与那国島であるのでこの場合は南の方向)を水源とする左舷灯浮標の南灯浮標と北灯浮標が設置されているが、船長のBは十分調査を行っていなかったので、これらの左舷灯浮標は油谷港を水源とするもので、その東側を安全に航行できるものと思っていた。
図3 海士ケ瀬戸
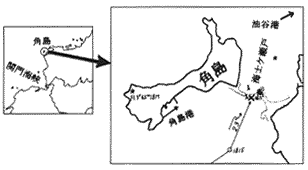
翌日午後1時、Bは単独で船橋当直につき、関門海峡を経て山口県西部沖を北上し、海士ケ瀬戸を通過することにして午後6時過ぎこれら右舷灯浮標から1カイリ南の地点で灯浮標を視認、その東側至近を通過するつもりで針路23度に変針した。
この針路は海士ケ瀬戸の浅所に向首する状況にあったが、それを知らず浅所に近づくにつれて次第に強まる南西流に抗して続行中、変針してから十分後浅所に原針路原速力(約10.7ノット)で乗揚げた。その時は日没の6分前であった。人命異状なし、船体は自力離礁、修理。
以上2つの肝例はちょっとしたミスが招いた重大な事故なので、この種事故の再発防止には、
(1)灯台の方位を自分の目で測る。
(2)必ず海図上でチェックする。
ことが大切である。