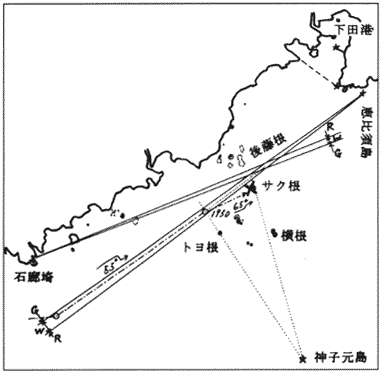★こんな乗揚げ事故は絶対起こさないように
7月のある日、490総トンの貨物船が、夕方、清水港を出港し京浜港へ向かった。船長Aは海上が時化てきたので自ら操舵操船に当たり、一等航海上と機関長を見張りに当たらせた。
午後7時半ごろ、石廊埼灯台沖、カイリの地点で針路84度に定め自動操舵で航行を始めて間もなく、須埼恵比須島指向灯の緑灯から白灯へ変わったので、その指向灯に向く55度に変針した。
指向灯とは通航困難な水道などの航路を.示すため、航路の延長線上の陸地に設置して白光で航路を、緑光で左舷危険側を、赤光で右舷危険側をそれぞれ.示すもので現在日本全国に、20基あるが、この恵比須烏指向灯(東航船用)は、石廊埼指向灯(西航船用)とともに昭和46年12月に設置されたものでわが国最初の指向灯である。
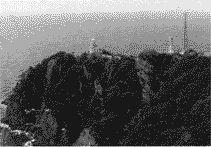
石廊埼灯台=(社)燈光会提供
したがって、前出の裁判官に説明した乗場事故当時は、指向灯はまだ設置されていなかった。
さて、本題の指向灯と険礁群との関係は図2のとおりで、船長Aが指向灯の白灯に向く55度に変針したのは、止しかった。(詳しくは、54.5度を中心に中1.9度で後藤根、サク根等を避ける水路を、示す)
だが、その後がいけなかった。変針後20分過ぎた午後7時50分ごろ、見張りをしていた一等航海仕等から「右方向に岩礁を視認し並航した」と報告を受けたAは、視界も良かったので「岩礁」を「サク根の岩礁」と思い込み、針路を65度に変針した。だが、報告を受けた岩礁はサク根ではなくそれより約1カイリ手前にあるトヨ根であった。
この時、Aはなぜレーダーの映像を見たり、肉眼で神子元島灯台の灯火などのコンパス方位を測って船位を確認しなかったのか。変針した65度の針路は、サク根に乗揚げる針路であったのだ。
そんなことに気がついていないAは、険礁群を抜けたと思い胸をなで下ろした6分後、船首はサク根に原速力(約10ノット)のまま乗揚げた。結果は廃船。
図2 下田沖険礁群