特集
 |
航路標識は泣いている |
舵社顧問 中川 久
今から30数年前、私が下田の巡視船舶長をしていたある日、裁判官一行が他の用件を兼ね、下田沖の航路筋 (俗に「海の銀座通り」といった)を視察するため私の巡視船に乗船したことがある。「海の銀座通り」は江戸時代の昔から東西を結ぶ重要な航路で海上交通が盛んなところである。
図1は今から二百数十年前の宝暦年間に描かれた地図を模写したもので、原図には下田のところに「此湊回船四、五百舳何風ニテモ掛」とかいてあり、当時の通航船舶がいかに多く、また下田が重要な寄港地であったかが伺える。
図1 宝暦年間の地図
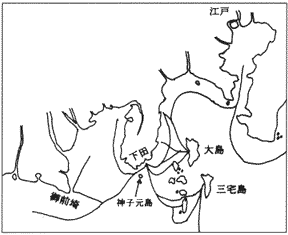
現在の航路
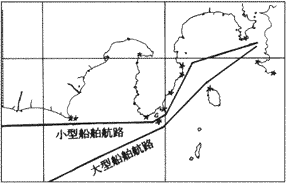
このため、昔から海難が絶えなかったという。私が下田在勤中もこの海域では衝突、乗揚げなどの海難が多かった。このことが裁判官の視察の一因になったのかもしれない。
さて、裁判官一行が本船に乗船するとその中にいた調査官が私のところにやってきて小声でいった「船長、今日はよろしくお願いします。本船が港を出て手が空いたところで、まず海上交通と陸上交通の大きな違いを簡単に説明してください。次に航路筋が海図上ではどこを通っているか、実際はどの辺か、そしてどのように輻輳しているか。最後に最近起きた海難の説明をしてください」
あとで分かったが、この調査官は私の数期先輩のシーマンであった。
本船は港を出たあと針路を石廊埼沖に向けた。折りから本船の周囲には10数隻の東航船、西航船が航行しており絶好の視察日だった。
私は、調査管の要求に沿うように説明したあと、最近起きた海難事故について次のとおり説明した。「ある日の夕方、500トン程の貨物船が、海上が平穏だったので清水港を出港し京浜へ向かった。
真夜中、石廊埼沖に差しかかると急に風が出てきて時化模様になった。
そこで船長は岸寄りの航路を通ることにした。この航路は風向きによって陸地に風がさえぎられ波立ちが少ない面、後藤根、横根等険礁群を通るので若干の危険を伴うが、小型船がよく通る航路であった。
さて、その船は保針に気をとられたのか、また、航路の選定が悪かったのか、いずれにしても船位の確認がおろそかになり陸岸に近すき過ぎて座礁してしまった。
幸い乗組員は、陸上に逃れ助かったが、船体は破損沈没した。この海域は石廊埼、神子元島などの灯台の灯光がみえており、いつでも船位の確認ができたはずである。
また、船位の確認ができないほど操舵操船に気を取られるなら、少し遠回りし若干時化られても十分に船位の確認ができる沖合いを航行すればよかった。
航海の安全を願って光り続けている灯台がこの海難を知ったらさぞかし嘆いたことであろう」
この時から30数年、航海計器や測位システムが進歩した現在、このような事故はほとんどないと思っていたが、最近、海難審判裁決録を見ていたら、この種の海難が後を絶たないことを知って驚いた。
そこで、その中から事故例2つを取り上げ解説を交えて紹介する。