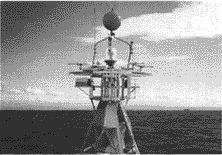接触事故の多い海域と主な原因
灯浮標への船舶接触事故の多い海域は、航行船舶が輻輳している東京湾、伊勢湾、瀬戸内海および関門海峡の4海域で、総事故件数は111件に及び全事故件数の約9割りを占めています。
また、この事故のうち加害船が判明したものは48件(38%)で残りの78件(62%)が当て逃げとなっています。加害船が判明した事故のうち加害船の申告によるものが26件と非常に少ない状況ですしこれらの事故による被害金額が300万円を超える事故も3件含まれており総被害金額は約5,000万円に上っています。
加害船の判明した質故の主な原因は、見張り、不十分・操船不適切といった操船者の、不注意によるものが大半を占めており、事故防止はもとより、事故後の速やかな通報など船舶運航者のモラルの向上が望まれます。
接触事故防止策
海上保安庁では、接触噂故防止対策として、関係団体への協力依頼、ポスターの作成等により、船舶運航者への注意喚起、モラルの向上を呼びかけています。
また、灯浮標には船舶が接触した衝撃により特殊な塗料が噴き出し、その船舶にしるしをつけるマ-キング装置を設置して、その船体に付着した塗料を証拠として加害船を見つけ出す方法をとっています。
さらに、平成9年度には衝突船自動撮影装置(写真13)を開発し、実用に向け試験中です、この装置は、灯浮標に設置したマーキング装置のセンサーと連動し、3台のカメラが一斉に加害船を撮影する装置です。センサーが動作すると、3台のカメラのフラッシュが4秒毎に光ため、加害船はもちろんのこと、付近の航行船舶も船舶接触事故に気づき、早期通報が期待されます。このようにして、灯浮標へ衝突した加害船の特定率を向上させる工夫をしています。
写真13 マーキング装置一本折損、防護枠約2?の曲損。平成10年1月19日06時ごろ事故発生