高機能化する航路ブイ
束京湾、伊勢湾、瀬戸内海等はわが国における物資輸送の拠点港であるハブ港湾を多数有し、これら港湾入出港する貨物船や大型危険物搭載船等が多数航行すろ輻輳海域ですが、効率的な輸送を目指して、今後さらに船舶の大型化・高速化が進むものと考えられます。これらの海域においては、船舶が集中して航行することとなるため海難発生のがい然性が向く、特に原油などの有害物質を運搬している危険物搭載船がいったん海難事故を引き起こした場合、海岸漁業や週辺地域の環境等への影響は計り知れないものがあります。
昨年7月東京湾で大型タンカー「ダイヤモンドグレース号」が浅瀬に乗り揚げ、原油が流失した事故は記憶に新しいところです。
海上保安庁ではこういった事故を未然に防止し、船舶の安全航行を確保するため、これらの海域に設置されている光波標識の機能についてその向上を図ることとし、平成10年度から東京湾を皮切りに既仔の灯浮標等の光力増大、同期点滅化、灯器のLED化および標識板のEL化(写真14)等の視認性向上の整備を実施しています。
同期点滅化は、同一航路の入口の灯浮標の灯火を同じタイミングで点滅させたり、航路の一方(例えば右舷側)のみを縦列で一斉に点滅させたりすることにより、標識そのものや航路の確詔をより容易にさせるものです。
灯器のLED化は、従来の白熱電球を使用した灯器からLED素子(発光ダイオード)を使用した光の発散角の大きい灯器に変更することで、灯浮標が大きく動揺しても見えやすくさせるものです。
標示板のEL化は、現在の灯浮標の番号の表示は灯浮標の名称板にペイントで記入しているため昼間しか確認できませんが、夜間においても標識の確認ができるようにEL(エレクトロルミネッセンス)という発光素子を用いた装置を開発し、番号等を発光表示させることにより標識の特定、確認を容易にするものです。(写真14)
なお、このような視認性の更なる向上を図るため、海上保安庁では、運輸省船舶技術研究所と共同で、コンピュータグラフィックス技術を用いた航路標識シミュレーションを開発し、海上交通の輻輳海域における灯浮標の効果的な配置・点灯方式等の調査を行い、利用者の立場での技術開発にも力を入れています。
写真14 EL表示装置。点灯状況の実例
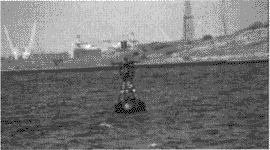
昼間の視認状況 |
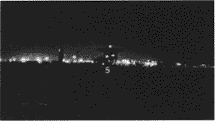
夜間の視認状況(ELで数字の5を表示) |
参観できる灯台と航路標識博物館
明治初期のころから海事思想の普及を目的として、灯台を開放してきましたが、昭和20年代になり一部の灯台に見学者が急増し、灯台職員がその対応に追われ、本来の業務に支障をきたしたため、灯台の見学を(社)燈光会が専従職員を配置して継続し、現在に至っています。
現在、一般に公開され見学できる灯台は、11カ所(図5)あります。(本誌に連載して紹介中)
これらの灯台は海岸線に美しくき立し、丁寧に手入れされた白亜の塔で、海の青、大地の緑にかすかな疑念を持たせることなく大自然に融合して、見る人たちの気持ち安らぎを与えてくれます。
また、見学できる灯台の一部(入道埼灯台、野島埼灯台、出雲日御碕灯台)には、(社)燈光会が開設した航路標識資料展示室があり、灯台の模型やパネル、パソコンやビデオ等を活刑して灯台の歴史・文化・仕組み・役割などを理解することができます。
さらに、全国には、地方公共団体が設置した灯台の博物館や資料館がいくつかあります。