因みに、このようなデザイン灯台と呼ばれているものが、現在全国に28基設置されています。(写真9、10、11)
写真9 御手洗港防波堤灯台(広島県豊田郡)

平成6年4月7日建立
江戸時代の灯ろうをイメージしている。地域の歴史的景観保存に一役買ったことにより、その周辺一帯が文化庁から重要伝統的建物郡保存地域に指定された |
|
写真10 淡輪西防波堤灯台
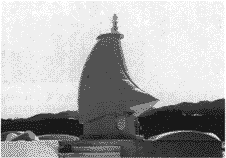
平成9年8月22日建立
ヨットの帆をイメージしている。国体(平成9年度開催)のヨットレース会場 |
|
|
|
|
写真11 小田原港新1号防波堤灯台
(神余川県小田原市)

平成10年2月25日建立
小田原提灯をイメージしている,江戸時代、箱根越えに重宝、現在では小田原市の観光シンボルとなっている |
|
*御手洗港防波堤灯台(H6・4、広島県豊田群)
江戸時代の建物が多く残っているこから、景観を考慮し「灯ろう」をイメージしている。
*淡輪港西防波堤(H9・8、大阪府泉南郡)
平成9年度の国体ヨットレース会場となったことにちなみ、ヨットの帆をイメージしている。
*小田原港新1号防波堤灯台(H10・2、小田原市)
小田原提灯をイメージしている
江戸時代、箱根越えに重宝、現在では小田原市の観光シンボルとなっている
悲鳴をあげる灯浮標
海上保安庁は、日本全国の港内外の主要航路および内海域や狭水道における浅瀬、暗礁等を明示するため、約1,500基の灯浮標を設置して海上交通の安全確保に努めています。
しかしながら、これらの灯浮標への船舶による接触字故が後を絶たず、この10年間で1,230件もの接触事故(写真12)しています。平成9年度においても、126件の接触事故が発生し、灯浮標の沈没事故、からの移動事故5件、それに夜間の標識機能を失う消灯事故6件が含まれています(別表2)

灯浮標船舶接触事故による損壊状況? |
|
← 写真12 → |
|
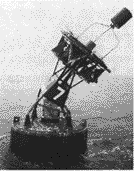
灯浮標船舶接触事故による損壊状況? |
別表2 過去5年間における灯浮標への船舶衝突事故種別内訳
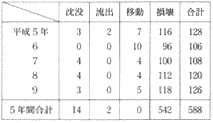
幸いこれらの事故による船舶の乗り揚げ等の二次災害は発生していないものの、灯火のみに頼る小型船舶にとっては、灯火のない灯浮標は航路の障害物のほかならず、存在するはずの灯浮標の消失および移動等は、航行船舶に大きな不安や座礁の危険をさらすことになります。