これからの発電システム
自然エネルギーの利用は、季節・天候等により左右される点で電気エネルギーの安定的供給面からは弱点といえます。具体的には、太陽光は冬期に弱く、波力や風力は冬期に比較的強いという傾向があり、特に太陽電池は、天候の影響が直接発電量に関係しますが、波力発電や風力発電は太陽電池ほど天候に左右されません。
こうした自然エネルギーの不安定さの弱点を補完し、安定した電源確保のため、海上保安庁では波力と太陽光、風力と太陽光を組み合わせたハイブリッドシステム(複合型)を導入しており、今後もより一層の活用を図ることとしています。
また、激浪が面接作用する箇所でも使用可能な太陽電池モジュールを有する「耐波浪ソーラーシステム」)(写真8)や灯浮標用の太陽電池単独の電源としての「灯浮標用ソーラーシステム」を開発したことにより、今後も利用を拡大することとしています。
写真8 関掛瀬(せっかけせ)北方灯標(長崎県南松浦郡若松町)
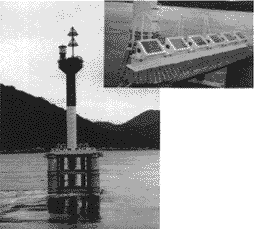
日本初 耐波浪ソーラーシステム採用
関掛瀬(せっかけせ)北方灯標(長崎県南松浦郡若松町)
太陽電池装置 耐波浪型
定格出力 12V 42V |
さらに、天候に全く影響されず地球と月および太陽等の宇宙引力エネルギーが源である潮流に着目し、周期的に変化するエネルギーを利用した発電装置を開発し、世界で初めての試みとして、平成8年1月から実用化を目指す試験を進めています。コスト面も含め試験に成功すれば、瀬戸内海、明石海峡、来島海峡、関門海峡など潮流の速い狭水道の灯浮標への採用を考えています。
地域に調和した灯台(デザイン灯台)
近年、各地でウオーターフロントの開発が活発化し、港湾を利用した地域振興が図られています。
最近では、港の防波堤に設置される灯台が顕著な目標物となり得ることから、建設に際しその地域の特色を表現したデザインを盛り込んでシンボル化し、地域の活性化を図りたいとの要望が地元の自治体などから海上保安庁に寄せられる例が増えています。
このため海上保安庁では、航路標識としての目的および機能に支障が生じない範囲で、提案者である自治体などと協力して、周囲の環境や景観にマッチした灯台をデサイン化し、地元の要望に積極的に応えるよう整備を進めています。
これらの灯台は灯塔本体の形状をデザイン化したもの、または標準的な灯塔にシンボルを表す形象物を付加したものがあり、地域のシンボルとして市民に親しまれているほか、地域の歴史的景観保存に一役買ったことにより、その周辺一帯が文化庁から「重要伝統的建物群保存地域」に指定された事例もあります。