自然エネルギー利用の始まり
日本で最初に光波標識用電源として実用化された自然エネルギーは、風力エネルギーで、1951年(昭和26年)蓋炸烏灯台(下関市)に風力充電装置を設置しました。(写真4)
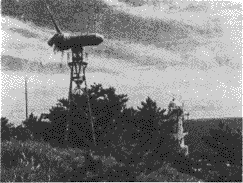
写真4風力発電装置(サブドー岬)
当時は、第二次大戦後で、石油燃料が、不十分な時代であり、ことさら離島、岬角への商用電源事情は悪く大型灯台の電源を安定的に確保するためには自然エネルギーに着目せざるを得ないところもありました。自然エネルギー利用の最初は、太陽電池であると思われがちですが、このころはまだ実用に値するシリコン太陽電池は、1954年(昭和29年)にようやくアメリカで開発されていたに過ぎず、国内では、いち早くこれを研究していた日本電気?により太陽光発電装置、1号機を1959年(昭和34年)に凋防筏瀬灯標(山口県上関町沖合)に設置しました。
さらに4年後の1963年(昭和38年)には灯浮標(鶴見第1号浮標H川崎市)にも採用しており、その後、数10基の灯浮標に採用しましたが、船舶衝突による太陽電池パネルの破損に伴うランニングコスト面から灯浮標への利用が一時中断されていました。
しかし、近年の半導体技術の急速な進歩に伴い、一般用太陽電池の変換効率も向上し、発電素子モジュールの小型化などで1991年(平成3年)から灯浮標への採用を再開しています。
また、波浪によって上下動ずる運動そのものをピストンとして用いて空気の給排気流を作り、空気タービンを回して発電機を駆動する波力発電装置(図2)を開発し1965年(昭和40年)に泉北第五号灯浮標(大阪府)に、1号機を設置しています。
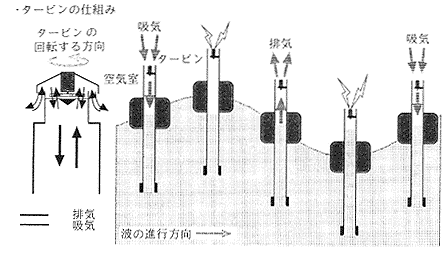
図2 浮遊式
その後、1995年(平成7年)には、固定標識(灯標)では、世界で初めて千葉県の小湊港灯標の電源に固定式波力発電装置(図3)を採用しています。
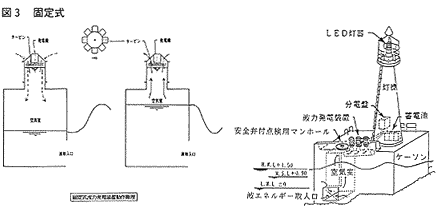
図3 固定式
以上の変遷を経て、風力(写真5)太陽光(写真6)波力(写真7)の自然エネルギーの利用が進み、現在では約1,500基の光波標識の電源に利用しており、これは全基数の28%を占めることになります。(図4)