このほか野島埼、品川、城ヶ島の三灯台もヴェルニーらフランス人技術者により建設されました。これらはいずれも灯塔の平面が四角形など、角形になっているのが特徴です。(写真2)
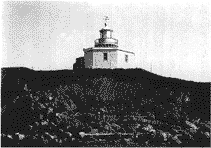
写真2 品川灯台
その後もイギリス人技術者リチャード・ヘンリー・ブラントン(1841〜93)が派遣され着々と灯台の建設がなされています。
ブラントンは、1868年(明治元年)から1876年(明治9年)に任期切れで帰国するまでの間に実に28基の灯台と2基の灯船を建設しています。これを構造物別に見ると、石造11基、木造11基(うち2基は灯船)、鉄造4基、れんが造4基であり、組積造のものは外形がよく似ており、灯塔は上にすぼまった円筒形で、その足元に扇形平面の付属舎(資材や燃料の倉庫)がついているのが特徴です。(写真3)
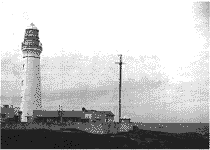
写真3 犬吠埼灯台
ブラントンは、数多くの灯台の設計、建設を手掛け近代航路標識のシステムを構築したことや測量、設計など土木建設の修技校を開設し技術者の養成も行ったことなどその業績は高く評価され「日本の灯台の父」として知られているばかりでなく、近代日本の土木・建築分野に大きな足跡を残しました。
外国人技師が帰国した後もブラントンに師事し、灯台技術研究のためイギリスに留学しエジンバラ大学で建築学を修めた藤倉見達、当時工部省からイギリスに留学を命じられ、灯台建築の指導を受けた石橋絢彦ら日本人の手によって洋式灯台の建設は進められました。
歴史的・文化的価値を持った灯台
日本における灯台の起源についてはすでに述べたとおりですが、明治期(1868〜1912)に誕生し今なお現役の航路標識として活躍している灯台は67基に及んでいます。これらの灯台は、長い歴史を生き抜いてきたが故に、その標識機能とは別に歴史的・文化財的に貴直な価値を有しています。
灯台施設の価値評価
現存する明治期の灯台は、すでに耐用年数を超過し、その立地が岬角や海上という厳しい自然環境とも相まって老朽化が進み、構造的に補強を必要とするものも数多くあります。
海上保安庁では構造補強などの改修整備に当たって、価値を損なうことなく適切に保全するために各灯台施設個々に歴史的背景などを明らかにして、その価値を評価することを目的に昭和60年から3ヶ年にわたり調査を行いました。
この調査は建設界や産業考古学の識者等から構成する「灯台施設調査委員会」を発足させ、日本史的、技術的、土木・建築史的、生活文化的、地域社会の資産的な視点に立ち、広義の文化財として調査を行い各灯台施設について「A〜D」の各ランクに分類しました。