特集
 |
海の安全を守る主役 |
灯 台
海上保安庁灯台部
灯台の始まり
灯台の生い立ち
わが国の灯台の起源については、古くは奈良時代のころから「みおつくし(水尾津串)」と呼ばれる水路を示す標識(図1)があり、その後、平安時代に入り、壱岐、対馬、筑紫に防人をおいて「のろし」を上げて海岸防備の固めとし、それがたまたま船舶に位置を伝え、昼は煙を上げ、夜はかがり火をたいて航行の目標としたことが記録に残っています。
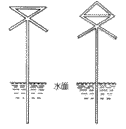
図1「みおつくし」の図 |
左の図は現在
大阪市章となっ
ている |
さらに江戸時代には、わが国独自の和式灯台として、石積みの上に小屋を建てその中で火を灯した「灯明台」や「かがり屋」と呼ばれる灯台が誕生し、その中でも慶長13年(1608年)に能登国福浦港に住む日野吉三郎という者が建てた灯明台は、石造りの小屋に木造の灯ろうをのせ油紙障子でこれを囲い、この中に菜種油を灯すもので、この灯明台が日本で初めて油を使った灯台といわれており、これらは江戸末期には約130基以上あったといわれています。
因みに、世界で記録に残る、一番古い灯台は、古代エジプトのトレミ王の代、紀元前279年にアレキサンドリア港の入口ファロス島に建てられたファロス灯台といわれています。
この灯台は、厚い城壁の内に、135?の塔がそびえ、塔内に多数の広間を有し、塔上の花岡山石に反射鏡を付け、そこでやし材を焚いて常時火を守り続けたもので、その灯火は、100キロ?離れた海上から見えたといわれています。
また、1477年までの1700年以上にわたって使われていたことからエジプトのピラミッドなどとともに世界七不思議の1つとして数えられています。
ファロスは、後に灯台その他の航路標識を総称する語となり、これがファロロジー(Pharologe=灯台建設学)の語源となっています。
西洋式灯台の誕生
現在のような灯台を建設するようになったのは1866年(慶応2年)5月、徳川幕府が米、英、仏、蘭と結んだ改税約書(江戸条約)の中で、交易のために開港した各港への海上交通の安全を確保するため、灯台の設置要求がなされたことに始まります。これにより翌年から灯台八基、灯船(船に灯火を掲げる。)2基の建設を行うこととなりました。
当時の日本には、.西洋式灯台の建設技術がなかったため、フランスやイギリスの技術者を雇い入れて、彼らの指導により建設が始められました。
日本の最初の様式灯台は、1869年(明治2年)にフランス人技術者フランソワ・レオンヌ・ヴェルニー(1834〜93)の監督のもと完成したのが観音埼灯台(写真1)です。
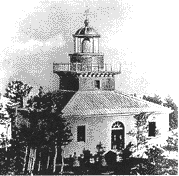
写真1 初代の観音埼灯台(明治2年初点)