
特集 40年の歩み
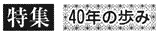
(1)本協会をとりまく年表
創立40周年を迎えた今、過去を振り返ってみることにも意義があろう。
40年の歩み?では、本協会を取り巻く主なできごとを中心に年表にしてみた。また、40年の歩み?では、補助事業として実施した調査研究事業の主なものを時系列に整理してみた。
いずれも、本協会の歴史と、時代ごとの関係する主なできごとを振り返っていただくときの参考としていただきたい。
-
S33・8・1
-
社団法人日本海難防止協会設立終戦後、わが国産業経済の復興とともに、海運・水産活動は一段と活発になり、わが国の周辺海域では船舶が輻輳し、厳しい気象・海象条件と相まって海難の発生も急増してきた。特に、昭和20年代後半から30年代にかけて、北海道南東海域におけるサケ・マス漁船409隻にのぼる大量遭難、国鉄連絡船洞爺丸の転覆沈没、暴風雨による事故および紫雲丸の霧中衝突沈没等、多くの人命を失う悲惨な海難事故が相次いで発生した。この事態を憂慮した運輸大臣は、昭和32年1月海上航行安全審議会に「海難防止の対策について」諮問し、同審議会は「啓蒙指導活動を強力に展開し、その実効をあげることが緊急な課題であり、そのためには新組織を結成する必要がある」旨答申した。これを受けて運輸省は、関係機関および海運・水産関係者と諸対策を検討した結果、世界に類をみない民間の海難防止団体として昭和33年8月1日に発足した。
●会員の構成…当初は海運・水産・造船・港湾・気象・保険・海員等全国組織を持つ52団体に限定されていた。
●役・職員の構成…会長、理事長、専務理事、総務課、業務課で構成され、役・職員総員数13名でスタートした。
-
9・26
- 狩野川台風(死者・行方不明者1、269人)
- 12・10
- 広報紙「日本海難防止協会報」創刊号を発行した
- 34・9・26
- 伊勢湾台風により、船舶11、027隻が遭難
- 11・1
- ロランA(太平洋ロランチェーン)業務開始
- 35・5・24
- チリ地震津波により東北地方太平洋沿岸大被害
- 36・2・1
- マイクロ波を利用したレーマークビーコン局(観音崎)業務開始
- 4・1
- 小型船舶職員養成事業開始(S39、日本船舶職員養成協会に移管即
- 37.11.18
- タンカー「第一宗像丸」横浜港で衝突炎上
- 38・2・26
- 旅客船「ときわ丸」神戸港和田岬沖合で貨物船と衝突
- 39・4・1
- 事務局を部制に移行
- 4・1
- 漁船・小型船訪船指導事業を開始
- 6・16
- 新潟地震(M7.5)
- 40・5・23
- タンカー「ヘイムーバード号」室蘭港にて衝突炎上
- 10・7
- マリアナ海域にて台風27号により漁船集団海難(行方不明郷人)「事故対策委員会」を設けて調査検討
- 41・
- 全日空羽田沖墜落・全日空松山沖墜落
- 42・3・/8
- タンカー「トリーキャニオン号一英仏海峡にて座礁
- 6・20
- 広報紙「日本海難防止協会報」を廃刊して、広報誌「海と安全」を創刊
- 7・1
- デッカ業務開始
- 9・1
- 船舶の油による海水の油濁の防止による法律の施行
- 43・4
- 日本国有鉄道からの委託業務実施(委託事業の始まり)
- 5・16
- 十勝沖地震(M7.9)
- 6・1
- 海水油濁防止事業の実施にあたり、当協会内に公害調査部(現海洋汚染防止研究部)を新たに設置した
- 44・1・5
- 鉱石運搬船「ぼりばあ号」野島崎東方海上で、船体損傷により沈没
- 4・1
- マラッカ海峡協議会設立
- 45・2・9
- 鉱石運搬船「かりほるにあ丸」野島崎沖にて船体損傷により沈没
- 3・17
- 単冠湾で流氷により漁船の集団遭難
- 11・28
- タンカー「ていむづ丸」川崎沖で爆発
- 46・6・6
- 本州四国連絡架橋航行安全調査委託事業開始(S46〜H9)
- 11・30
- タンカー「ジュリアナ号」新潟沖で座礁、原油約7、200kl流出事故
- 48・5・19
- カーフェリー「せとうち」播磨灘で火災、沈没
- 7・1
- 「海上交通安全法」の施行
前ページ 目次へ 次ページ
|

|