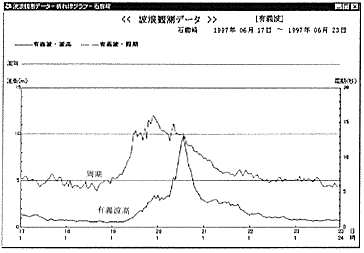海の気象
安藤 義彦
(気象庁気候・会用・気象部海上気象課)
台風の高波
はじめに
気象庁は海上気象情報を毎日作成し、JMH(気象庁第一気象無線模写通報)などで提供しています。北西太平洋の波浪情報として「外洋波浪実況図(AWPN)」と「外洋波浪時間予想図(FWPN)」が、また、日本近海・沿岸の波浪情報として「沿岸波浪実況図(AWJP)」と「沿岸波浪24時間予想図(FWJP)などがあります。
これから台風シーズンを迎えますが、気象庁は東経100〜180度、北緯0〜60度の領域内に台風があると、台風情報や予報警報を出します。台風に伴う波浪は特に高くなることが多いため、正しい知識を持って海上気象情報を理解し、安全を図る必要があります。ここでは沿岸波浪図や気象庁沿岸波浪計の観測資料をもとに台風の高波について説明します。
平成9年の台風による高波の事例
日本近海における気象海象が原因の海難は、大きく分けて、5月から8月にかけての霧によるもの、主に暖候期の台風に伴う強風高波によるもの、主に寒候期の発達した低気圧に伴う強風・高波によるものがあげられます。
平成9年は台風が早い時期から日本に上陸(6月に2個)して話題となりましたが、年間の発生数は28個で平年並みでした。平成9年の高波は気象庁が設置している沿岸波浪計(全国11ヵ所)での観測によると、それぞれの観測点の観測開始以来10位以内に入る記録が10例あり、そのうち台風によるものは8例でした。
統計的にも、日本における高波は台風によるものが最も多くなっています。平成9年1年間で全国で最も高い高波(有義波高=注)を観測したのは静岡県石廊崎で、6月20日に台風第7号により9.8メートルを記録しました。また、高知県佐喜浜では7月26日に台風9号による高波8.7メートルを記録し、その観測点での最高記録を更新しました。
台風第7号による石廊崎での波浪の様子を見てみましょう。台風7号は大型で強い勢力を保ちながら南大東島の東海上から四国沖を経て北上、中型で並みの勢力となって20日11時ごろ愛知県に上陸しました。その後本州七を北東に進んで、同日夜には三陸から海上へ出ました。台風が日本の南海上にあった間、大型で強い勢力を保っていたので、その中心付近の高波は非常に高くなり、波浪実況解析(図=沿岸波浪図)によると、四国南方沖にあった19日9時には、中心付近で有義波高が11メートル以上(最高となった21時には12メートル以上)ありました。石廊崎は台風中心のコース右側近傍にあたって、最も高い波を記録しました。
図1 平成9年6月19日09時の沿岸波浪図
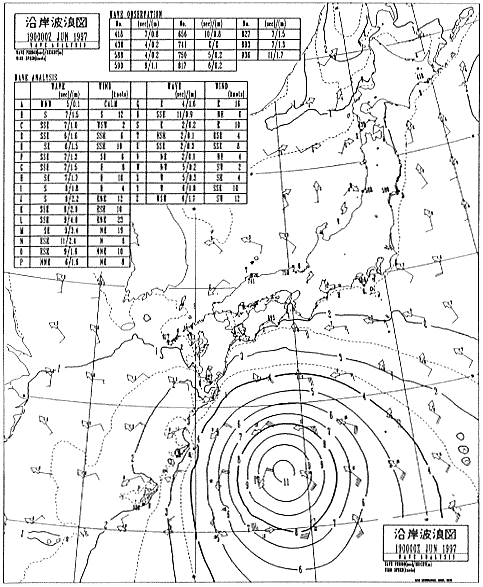
図2は6月17日から23日にかけての石廊崎沿岸波浪計による有義波高と周期の観測値です。台風がまだ四国の南方沖にあった19日朝ごろから周期が長くなり始め、夜には10秒前後になりました。この周期の急な変化に比べて高波の変化は、19日中は穏やかですが、このような周期の変化は、この時点で台風からのうねりが石廊崎に到達し始めたことを示しています。
台風が本州に上陸後、付近を通過した20日午後、石廊崎では急に波高が高くなって14時には有義波高の最高値9.8メートルを記録しました。最大波高は有義波高よりさらに5割以上高く、15.9メートル(20日15時)にも達しました。
図2 石廊崎沿岸波浪計による波高と周期の記録