このなかでとくに留意すべき点として、(1)高齢化の速度が異常に速いということ、(2)老年人口の比率が著しく高く絶対数が多いこと、(3)増大する高齢人口のうち、とくに80才以上の高齢者が激増していくこと、(4)これまでの高齢化社会は従属人口指数(年少人口と老年人口で割った指数)が史上最低まで低下していくなかで高齢化を迎えたのに対して、21世紀の高齢化は従属人口指数が急速に高まっていくなかで展開していくことなどがあげられる。
これに加え、今後の経済、社会の変動と関連する人口の動きのなかで、これからの高齢化社会にいくつかの留意すべき問題が生じてくる。今後、核家族化がいっそう進み、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が増えるなどの事情によって、家族形態や家族機能が変化し、併せて経済構造の変化、高学歴化、女性の社会参加機会の増大などが顕著になっていくであろう。
図1 老年人口の推移と予測
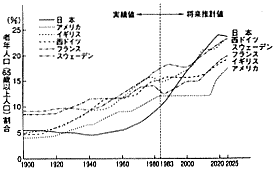
資料:日本は総務庁統計局「国労調査」及び厚生省人口問題研究所の推計に、外国は国連資料(UN,Population Studies)に基づく。
出典:地方自治政策研究会編「地域社会と高齢化化」(平成元年)
このような変化とは別に、日本の高齢化社会は、現在とは異なる経済・社会・文化などの発展(衰退)状況との関わりのなかでとらえることも重要である。例えば経済の低成長やサービス経済化の進展が高齢化にどのような影響を与えるかとか、あるいはマイクロ・エレクトロニクスやロボットなどの先端技術の発展や情報化(コンピューター)社会の進展が高齢化社会に与える影響など、本格化する高齢化社会をとらえるいろいろの視点がありうるのである。
その1つに高齢化社会に対応した海洋性レクリェーションの整備課題がある。海洋性レクリェーションヘの参加人口は極めて大きく、将来の新規参入人口と高齢者分を加えると巨大なニーズが期待できる。
しかしながら、高齢化に伴う身体機能および精神の機能低下による高齢者参加人口の減少が推測され、65から72才の高齢者参加人口数は環境が十分に整備されば減少率は少ないといえるだろう。海洋性レクリェーションにおいて高齢者の参加人数が増加すれば、必然的にさまざまな環境の改善が要求されるようになり、また参加する高齢者が安全に快適に活動するためには、施設整備にとどまらず周辺の各種インフラやエレメントもさまざまの面で改良を加える必要がある。
さらに、それらの整備要請のなかには単にハードの面だけではなく、高齢者をテイクケアするソフト面の整備もあわせて行わなければならない。このように考えると、高齢化社会における海洋性レクリェーション整備は巨大な経済的構造を創出し、あわせて健康な高齢者による介添えを必要とする高齢者のサービスという新たな雇用機会も発生する可能性がある。
海洋性レクリェーションのシステムは、おおむね健常者や若者を対象とする施設、機器、道具、アメニティ、ファッションが主流となっている。
したがって高齢化を契機に現れる高齢化社会の課題は単に増大する高齢者の問題とか、あるいは高齢者の老後生活に欠かすことのできない保健、福祉あるいは年金などの所得保障の問題だけでなく、より広く多面的にとらえる必要がある。

ライフセイバー達の救助訓練の様子。
人命救助には水上バイクが最も活躍するという