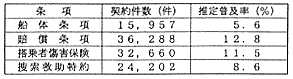特集 プレジャーボートの保険を考える
−プレジャーボートが市民権を得るために−
有限会社アンズコーポレーション 代表取締役 佐野嘉男

佐野 嘉男氏
商船や漁船の海のプロはそのほとんどが保険に加入しているが、海のアマのプレジャーボートでは、一部を除き保険を利用していない。それはどうしてなのか。
プレジャーボート向けの保険にすべてのプレジャーボート愛好者に加入してほしいものだ。そうすればプレジャーボートが市民権を得ることにつながると思うのだが……。
はじめに
今年もまたプレジャーボートにとって最適な季節がやってきた。真夏の海で自分のブレジャーボートに乗ってセイリングや釣りを楽しむのを、無上の喜びとしている人の気持ちは良く理解できるし、お金と暇があれば自分もやってみたいと思っている人もたくさんいるだろう。
人々の生活が豊かになり多様化していくのに伴い、プレジャーボートが盛んになっていくことは大変結構なことだと思うが、プレジャーボートで遊ぶ人が増えボートの数も増えてくれば、事故もまたそれに比例して増えるのも自然の成り行きなのかも知れないが、大変困ったことだと思う。
海を仕事場としている海運業者や漁業者は、海の恐ろしさをよくわきまえているからこそ操船技術を鍛練するばかりでなく、事前の準備を人念に行うのに対し、たまにしか海に出ないプレジャーボート愛好者は、海を甘くみているわけではないのだろうが、遊びたい気持ちが先行してついつい準備が甘くなる結果であろうと思う。
それでは、準備が甘くなる穴埋めに保険を十分掛けているのかというとこれもまったく逆で、海のプロ達が100%保険の機能を活用しているのに対し、海のアマチュア達は一部の心ある人を除いてほとんど保険を利用していないのが実態である。
現在、日本損害保険協会で集計している統計の中に、プレジャーボート関連の保険だけを抜き出したものは無いので、わが国におけるプレジャーボート関連保険の普及率をつかむことはできないが、財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が発行したパロー・マリン・レジャー97、98年版に、同協会が推定した普及率を掲載しているので紹介しよう。
データが古いので恐縮ではあるが、他に適当なデータが無いので参考にしたい。
その後日本で最大の収容隻数を誇る公共マリーナである「横浜ベイサイドマリーナ」がオープンしたが、同マリーナは施設利用契約の中に賠償責任保険の付保を義務付ける条項を盛り込んで、関係者から高い評価を得ており、その後次々にオープンした大型マリーナも同様の条件付けをした模様なので、プレジャーボート関係保険の普及率はかなり上昇したものと推定される。しかしながら、プレジャーボートの大半はマリーナ以外の場所に係留されているので、全体として普及率が大きく伸びてきたとみるのも早計だろう。
海の新規参人者であるプレジャーボートが海の先駆者である商船や漁船から邪魔者扱いにされている現状があるが、プレジャーボートの保険が十分普及していないこともその原因のつとして挙げられるのではないかと思う。
なぜかといえば「プレジャーボートは助けられても何のあいさつもない」とか「夜中に漁網を破られて逃げられた」といった海のマナーの欠如が問題視されるが、突き詰めて考えればボートオーナーが事故後の交渉の煩わしさと多額の求償を恐れる気持ちから、眼前の事実から逃げ出そうとする結果であって、十分な保険が付いていればその面の心配をする必要はまったくなく、正に“衣食足りて礼節を知る"と信じるからである。それでは、なぜプレジャーボートの保険は普及していかないのだろうか。
それに対する理由としては、オーナー側に、自動車ほど頻繁に乗らないし自分は事故を起こさない自信があるから保険は必要ないと考える人と、保険のてん補内容に、不満があるし保険料も高いから保険は要らないという人がいるからだと考えられる。
そこで、まず現在保険会社が売り出している保険の種類とその概略を説明し、次にどの点がオーナーにとって不満であるのか、また保険会社はどう考えるのかを整理して、最後にどうしたらプレジャーボートの保険が普及するかを模索してみたいと思う。
プレジャーボート関連保健の普及率
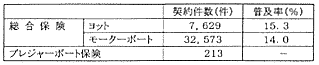
ヨット・モーターボート総合保険の条件別普及率