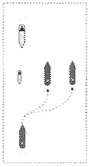操船者の意識と評価指標
いくつかの条件下で船舶交通の流れが模擬、再現されると、次には比較・評価の段階を迎える。価値を判じるために当てる物差しを評価指標と呼んでいるが、評価の手順として総論的にも触れたように、何をもって測るかは重要であって、立場や次元の異なる物差しを使えば、結果は一変する。
船舶が混み合っている海域では安全性も阻害されやすいとの観点から、単位面積当たりに存在する船舶数、すなわち「密度」に代表される類の評価指標で比べれば同航する船舶4隻を配置した状況での数値が高くなり、衝突の危険や避航操船の負担で測れば横切り船を含む3隻を配置した状況が高くなって逆転する。では、「密度」をもって測ることは間違いであろうか。
実は「密度」で比較評価する場合には、「存在する船舶の針路や速力、大きさ等のバラツキ具合(分布状況)が同じであるならば」といった前提条件が必要であり、これに合致しない例を挙げたに過ぎない。
この前提条件を満たす複数の海域を「密度」で比較評価することは誤りではないが、法規制等によって整流されている海域と針路が錯そうする海域を同一に論じることはできない。
そこで、針路や速力、大きさ等のバラツキを考慮した上で、衝突確率や衝突危険度を表わす手法や評価指標が提唱される段階へと進むことになる。衝突危険度の算定方法は幾つか提唱されているが、いずれも相手船との方位変化など通常の航海で操船者が意識する測定量を用いており、個人差の取り込み方などの細部にわたる相違を捨て去れば、いずれの指標値を用いてもよいものと思える。
ただし、1船対1船の衝突危険を評価するものであるから、複数の船舶と見合い関係になった場合の処理については、別途工夫が必要になる。
図6において、相手船の1隻ごとに着目すれば、(a)では2隻の反航船と衝突の危険が顕在するが、(b)では1隻となる。しかし(a)では、例えば右に変針すれば2隻の反航船との衝突危険は1度に解消されるが、(b)では右に変針することがはばかられるので、単純に衝突危険のある船舶数だけでは測れない。さらに(a)の場合を例にとれば、大きく変針すれば衝突の危険度は下がるが、運航上の損失は増加し、操船者に負担を強いることになるので、双方の観点から評価する必要がある。適切な避航操船によって得られる安全な船舶交通は、操船者各位の努力の賜物であり、その中に潜在する負担は、外部から観測した衝突危険だけでは測れない。
図4ミクロシミュレーションのイメージ
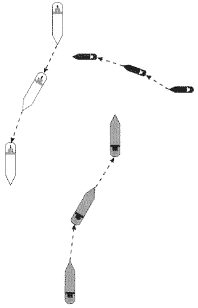
図5何で測り、比較するか?


図6複数の船舶との出会い評価