一方、個々の船舶の行動を詳細に模擬すれば、計算処理時間は重荷となり、取り扱う海域の広さにも自ずと限りがある。モデル化の姿勢も、計算対象海域も、そしてシミュレーションの結果から得られる情報も、それなりにマクロであり、またミクロであって、なかなかに意を得た表現だと思う。
ただし、電子計算機の処理能力は日進月歩で成長しており、ミクロシミュレーションモデルでも十分に広大な海域を対象に計算処理できるようになったが、モデルのさらなる精巧化に伴う負荷の増加とイタチごっこの様相も呈していて、人の行動を模擬することは相変わらず難しいと言わざるを得ない。
現在、日本海難防止協会の各種委員会で検討の用に供されるマクロシミュレーションの代表例はネットワークシミュレーションモデルであり、大ざっぱではあるがそのイメージを図3に示した。
リンクの部分直線状の航路であり、ノードが交差部に対応する。リンク部は対象海域に応じた幅と長さを持つ長方形としてモデル化され、その中に存在する船舶の占有面積比率などによって輻湊状況(利用率など)が表わされる。交差部に相当するノードでは、他船が存在すれば「待ち」が生じるものとして評価される。
図3ネットワークシミュレーションのイメージ
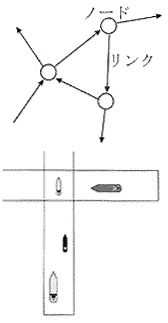
状況の変化は、船舶が新たなノードやリンクに進入するという事象(イベント)によって生じるから、このイベントに着目してシミュレーション計算を進めていけばよい。このような時間の切り方によってシミュレーションの中での時刻を進める方法は「イベントスライス」と呼ばれるが、行動模擬の簡素化と合わせ、長期間にわたる交通流の予測計算も比較的短時間で実行できる。
一方、ミクロシミュレーションでは個々の船舶の挙動も模擬され、衝突や乗り上げの危険があれば、適宜変針・変速などの避航行動を採りながら目的地へ向けて航行させていく。他船との衝突や乗り上げの危険判定あるいは行動を選択する方法が異なる幾つかのモデルがあるものの、位置関係や針路、速力など、時々刻々変化する情報に基づいて計算処理するため、シミュレーションは一定の時間間隔で切りながら進めていく。このような進め方は「タイムスライス」と呼ばれるが、細かく区切れば時間がかかるので、操船者の判断時間や船舶の運動特性を勘案して、5秒から15秒程度の間隔にて実行されている。
変針、変速時の応答の遅れも模擬するモデルがあって、随分と精巧なシミュレーションが実行されるようになったが、行動選択の理論はすべての船舶に同一であり、個人差はないのかと指摘を受けたりもする。
行動選択にバラツキを取り込んだり、衝突危険を判定する基準値を検証するなど、細部にわたって検討するべき宿題も多いが、半面では、複雑なモデルを作るほどに原因と結果の間が不鮮明となり、対策を講じるべき点が判り難くなるのではないかと、心配をする段階までに至っている。なお、すべてのシミュレーションモデルがマクロモデルとミクロモデルに分類できる訳ではなく、両者の特質を生かしながら、中庸を狙うモデルも開発されていることを付言しておきたい。