しかしながら、陸上から観測する実態調査結果は事実の数値化としての意義と重みを持つが、当該海域を航行する操船者の視点には立てず、また、大型海洋開発プロジェクト等に伴って必要となる予測的な評価ができないなどの限界がある。この欠点を補う一つの方法がモデル化である。
モデルは、模型や操船シミュレーターあるいはモデル地区などの具体的なものや、数式による抽象的なものなど多くの種類に分類されるが、本質的には注目するべき機能のみを浮き彫り的にとらえ、因果関係を明確にしながら原因と結果の評価へと進むための手立てであり、明確さを担保するためには実システムを簡略化することが多く、「そんなに簡単なものではない!」と、この段階でご批判をちょうだいすることにもなる。科学とは、細かく分けて学究することであり、しかる後に統合され、現象を明らかにする姿勢であるから、今しばらくはご理解とご協力を賜りたいと思う。
評価の手順を示した図では、モデル化に続く作業として評価指標の選定をあげたが、昨今は評価の主人公(主体)を操船者に置くことが多くなっており、操舵の大きさや頻度あるいは航路からの偏位量など、端的な物理量を指標として操船者の負担を類推評価するだけではなく、操船者の安全感覚や危険感についてもモデル化が進み、定量的な評価を目指す傾向にある。
無論、船舶交通の再現と評価の2段階に区別することが適当ではない手法もあるが、何をもって測るかは重大事であるとの認識から、無理を承知で別項目とした。長さを使えばウナギや太刀魚には有利に働く不公平な例は分かりやすいが、時としてモデル化により失われた項目が評価指導に現れることもあり注意を要する。
モデル化と評価指標の選定がすめば峠を越えたようなものであって、事例によっては複数の代替案を作成し、適用評価と妥当性のフィードバックを適宜繰り返し、精度を高めていくこととなる。以上は一般論であるが、予測評価を可能ならしめる船舶交通の模擬・再現モデルと操船者の内面をモデル化した評価指標について、もう少し例をあげながら紹介する。
シュミレーション
船舶交通は経済活動に基づいて発生するから、大都市周辺海域では朝夕に、中間地点では深夜にラッシュを迎える等、流れとしての特性を有するが、個々の船舶の出会いについては多分に当たり外れがあって画一的ではない。輻湊する海域ではサイコロを振る回数が多く、好ましくない目が出る確率も高い訳であって、確率的な問題として取り扱うことが実際の感覚とも合致する側面を持つ。確率と確率が重なり合うと、数学的にはなかなか解き難い問題になってしまう。
そこで、すでに述べた将来的な予測評価の必要性ともあいまって、船舶交通の統計、確率的な特性を取り込みながら、計算機の中で交通流を模擬、再現するシミュレーションモデルの出番となる。
船舶交通シミュレーションモデルは、計算機の出現と普及にそれほど遅れることなく昭和43年ごろからる提唱されその成果を見ることができるが、当初は、「シミュレーション」なる用語自体が不可解さをす醸しながらも流行したきらいがある。
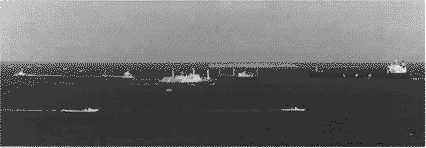
船舶の輻輳する浦賀水道