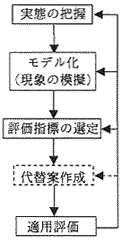船舶交通の特徴
本題に入る前に、安全性評価の対象となる船舶交通の特徴について少し整理をしておきたいと思う。一言で言えば、自由にして鈍重である。
海上衝突予防法や海上交通安全法など特定の優先権を定めるものはあるが、大小を問わず自由に平等の権利を持って航行できることが原則であり、飯島幸人先生は陸上交通と対比させる意味から「乳母車からダンプカーまで、同じ権利で同じ道を利用」している状況に例えておられ、海に疎い方々の理解を得るのに手っ取り早い表現であろう。
また、1次元的な陸上交通とは異なり、2次元的な広がりを持つ船舶交通は、出会いから衝突を避ける段階まで多様性に富み、変針、変速、その組み合わせがあって、反射的にブレーキを踏めばよい訳ではない。
このように陸上交通に比して、行動の自由度が大きい半面一般的な船舶の運動性能は鈍重であり、適切な行動の決定と時期の選択に関し、操船者に多大の負担をかけるとともに、行動の適否の評価を難しくしている。
過日、新幹線車中で広島大学の小瀬邦治先生と話した折りに、制御能力の劣悪さを端的に表現する指標を教えていただいた。計算上の数値や仮定に多少の甘さはあるが、参考までに自重と馬力の比率をイラストにして見た。
無論、船舶の種類も多く千差万別ではあるが、ひとたび海難事故を起こせば多大の被害をもたらす恐れがあるVLCCなどは、赤子同様の力の無さ
であり、これまた船舶交通の特質を伝える道具として利用いただければと思う。
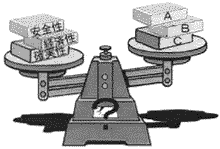
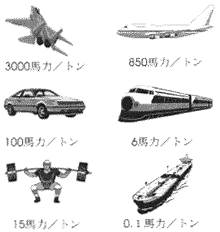
評価の手順
船舶交通は定性的な要素と定量的な要素を含む代表的な社会システムであるが、一般的な評価手順は図1のようになる。
すべての要素が定量化され計算可能な、純粋に技術的なシステムとは異なり、原因と結果の間に明確な関連性がなく、しかも種々の要素が複雑に絡み合う社会システムでは、結果を評価に結び付ける方法が手っ取り早い。体系的な交通実態調査は昭和39年から始められ、交通量などの基本統計データが取得されるようになった。船舶が集中する海域は衝突等の危険性も高いものとして、しばらくは基本統計量が評価のための指標として利用されることになる。
図1 評価の手順