絵で見る日本船史
ぶら志゛る丸
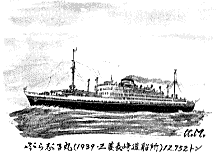
昭和12年4月1日実施された日本政府の優秀船建造助成の適用を受け、大阪商船では西廻り世界1周南米線用として2隻の貨客船を建造、第1船あるぜんちな丸は同14年5月31日、三菱長崎造船所で完成しこの船は戦前日本の誇る花形豪華船であった。
この2隻は後年大阪商船の専務取締役に就任された和辻春樹博士設計の船で、その容姿の優美さは当時博士が手がけた社船80余隻中の最高傑作といわれ、南米移民船の集大成とも伝えられている。
かねて有事の際には軍用空母に改装されるよう設計された姉妹船で、あるぜんちな丸は太平洋戦争中の昭和17年12月から、三菱長崎造船所で翌18年11月まで1か年間に渡る大改造工事により、特設空母海鷹として生れ変り、主に航空機輸送や練習機訓練用母艦として瀬戸内海西部で活躍した。
第二船ぶら志る丸も三菱長崎で建造された総屯数12,752屯のあるぜんちな丸と同一設計の船で、機器類総て国産品で、設備や調度品等大同小異はあるが、ぶら志る丸の特別室・鎌倉と宮嶋、貴賓室・日光は日本情緒豊かな、豪華で絢潤たる装飾が賞讃されていた。
昭和14年12月23日完成後、横浜と神戸で盛大な竣工披露宴が行われ政、財、官はもとより業界、商社、顧客など多数が招待され、翌15年1月11日横浜を出帆し南米処女航海に就航した。
ぶら志る丸による神戸サントス間の航海日数は、従来の最短記録46日を10日間短縮し36日で走破、世界一周を3ヶ月で達成し寄港各地で熱烈な歓迎を受け、航海途上の南米と北米では当地の官公民顧客や、在留邦人多数を招待し大阪商船主催の、盛大な就航祝賀会が挙行されたのである。
昭和15年9月15日神戸発の第3次航を最後に、国際情勢悪化の影響で外国航路は中止となり、翌16年1月から大阪・大連航路に配船されていたが同年九月四日、海軍に徴傭され横須賀鎮守府所属の運送船となり、連合艦隊に随伴し各地への兵員輸送に従事した。
翌17年5月28日サイパン島で海軍陸戦隊を満載し、13隻編成の船国に加入、ミッドウエイ攻略作戦に出撃したが、途中6月5日『作戦中止、反転せよ』の命を受けグアム島に帰投、引き続き内地に帰還、横須賀からソロモン群島の前進航空基地建設に出動する設営部隊4千名と、建設用資材を満載しラバウル基地に向つた。
その航海途中に行先変更の命でトラックに入港、設営隊と積荷の総てを揚陸し、完了後『急速内地に帰還し特設空母に改造』の命を受け、8月8日午後4時横須賀に向け出港したが、翌5日午前1時トラック島の北西方110浬の地点で、米潜グリーンリング号の魚雷2本を左舷中央部に受けて、船首を天に向け船尾から垂直に棒立ちとなり、7分足らずで海底深く吸い込まれるように沈没した。
当時乗組員、兵員、便乗者など計389名が乗船中で、大野仁助船長以下乗組員57名と兵員等131計188名が船と共に殉死し、残り200余名が遭難後20日ククナン間漂流、奇跡的に哨戒艇第十拓南丸に発見され大半が救助された。
大阪商船では当時戦渦で喪失した船の沈没情況などを、生存者の証言に基づき嘱託画家大久保一郎画伯の手により油絵70点余を制作し保管されていた、と同社発行の『風涛の日日』に書かれている。
戦後この絵が発見された時大阪本社の保管倉庫の冠水で相当数の修復不能な作品と、行方不明等で展示可能な絵が37点、その中にぶら志る丸の絵が2枚あった。
1枚は船首を上に棒立ちで沈没する船の姿、もう1枚は沈没寸前の船橋上で両手をあげ万歳の形で従容と死地に赴く大野船長の厳粛な最後が画かれている。‐合掌-
松井邦夫(関東マリンサービス)