K汽船所属の大和丸は内航の鋼材運搬船として昭和37年7月に作られた沿海区域の貨物船であった。今回の就航のために近海区域に資格変更したが、航海機具なども北洋航行に必要なロランも方向探知機もない。
また約40日の就航予定日数に必要な食糧や水、燃料油などを十分積み込めるスペースもなかった。乗組員24人分となると従来使っている冷蔵庫や野菜庫には収めきれないので、じゃがいも、たまねぎ、キャベツなどはボートデッキに積んでカバーをかけた。
飲料水なども空船時に荷足水槽(バラストウォータータンク)として使用している水槽を清掃して積み込んだ。
また、レーダーは映像の範囲が25カイリであったが、北洋就航前に50カイリのものに新替した。
海霧の多い6月の北洋で、船位の測定に必要なロランや方向探知機もないのでいろいろな不安はあったが、その感情をおさえての北洋就航であった。
6月11日、朝のあいだ少し太陽が見えていたが、午前九時ころには濃霧になって見えなくなった。
船尾に引いている特許測程具(速力を推進する器具)は誤差が多く、速力の推測にはあまり参考にならない。
午後9時40分ごろはじめて大津丸から無線電信による指示を受け、309漁区(北緯52度、東経168度)に向け、風圧差など右へ3度ほど加減して真針路53度に変針する。
まず心配したのは大津丸との交信が順調に行えるかどうかではあった。何とかスムースに連絡することができてひとまずほっとした。
6月12日午前6時ころ黄色い船体の独航船と行き会う。朝から雨が降っている。
日本海にあった低気圧が980ヘクトパスカルまで発達して北東に進行中で本船の予定針路上に向かって進んでいる。
夕刻になり南東の風が強くなってきて波浪が高くなり、うねりが出て海上は荒れてきた。
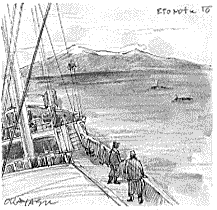
午後2時ころ2隻の独航船と出会ったが、かなり揺れながら波沫をあげていた。
6月13日、本船の進行方向に接近してきた低気圧の影響を受けて、強くなった風は本船の右舷側から吹いている。
風下への圧流の程度が心配される。霧は依然としてかかっていて視界は約1カイリである。
午前4時に真針路を56度に変針する。
何といっても当面の不安は三転目の最後の針路にはいってから、予定の時刻に母船をキャッチできるかどうかということであった。
松輪島をレーダーの映像でとらえ、実測の船位を確認して3昼夜近くになる。
霧の日が多く天測によって実測船位を得る機会に恵まれず、もっぱら推測航法に因るしがなかった。
会合の予定時刻を1時間ほど過ぎた午後9時ころ、母船と仲積船らしい船影をレーダーの映像でとらえることができた。
近づいてみるとまさしく大津丸であかりに照らされいるファンネルマークの赤いHの字が見えてきた。
私にとって北洋仲積船就航ははじめてであり、いろいろな不安を抱えてきただけに無事母船に会合することができた。さっそく漂泊待機することになりほっとした。
“霧のなか航りきたりて北洋の作業灯明るき母船に近づく”
(つづく)