
北洋就航(1)
山本 繁夫
岡安 孝男画
社会の進歩とともに技術革新のさまざまな発展によって、GPS(汎地球測位装置)は船舶の航行・航空の分野・自動車など広く一般に普及されるようになった。現在位置なども簡単に求められる今日このごろである。
私の長い海上生活の多くは、港から港へと荷物を運ぶ貨物船の乗組員としてであった。1回だけ貨物船で北太平洋へ出漁中の北洋漁業のさけます事業船団の母船、H水産所属の大津丸(8,030総トン)に沖積船として就航したことがある。
本船が就航した6月・7月の北太平洋は霧の多い季節で、GPSなどはなく、当時普及していたロラン設備さえもない小さな船で、海霧の中に操業中の母船に推測航法で会合できるだろうかという不安があった。当時のことを回想してみようと思う。
当時乗船していた貨物船大和丸(996総トン)は昭和46年6月3日午前7時30分東京港品川岸壁Fバースに着岸。さっそく午前8時から積荷役作業をはじめた。缶詰製造に使用する空缶6万ケース、缶蓋2,000ケース、新巻箱2,000ケース、塩54トン、ベニヤ板850枚などが積荷で、当日は午後5時に積荷役を中止した。
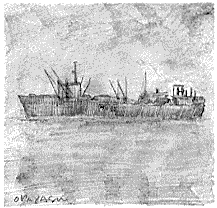
6月4日午前8時より積荷役を再開、午後5時積荷役を中止した。5日午前8時より積荷役を再開し、午後4時に積荷役を終了した。午後6時東京港を出港、さらに資材を積むために釧路港へ向かった。
6月8日午前8時45分釧路4号岸壁に着岸し、漁網400反(12トン)補水、補油、食糧などを積み込み、午後7時釧路港を出港し北洋で操業中の大津丸に向かう。6月10日、作目は霧中航行であったが、明るくなりはじめた午前3時ころからはかなり視界がよく見えるようになった。現れてきた新知島に富士山のような円錐形の山が見えるが、まだかなりの雪が残っている。
海上に行会船はないが、時折くじらが潮を吹いている光景に出会った。付近には活火山の噴煙と思われるのも見えた。東京周辺で初夏を見てきた自分には春まだ浅しといった感じがする。
気温5度、水温3度である。北海道のノサツプ岬周辺などで、日本の漁船とロシアの警備艇との間にいろいろな問題が起きてゆれている報道を聞くと、これらの島々に対してもいろいろ複雑な感情が生ずる。23時50分、松輪島東端に並航したあと真針路88度に転針し、330漁区(北緯48度10分、東経151度50分)に向ける。