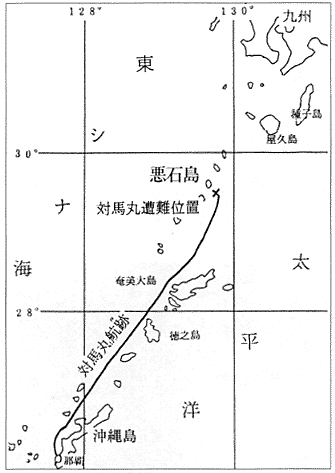船尾には一般疎開者が人り、学童は船首の第2船倉の中デッキに人れられたとのことです。こう配の急なはし子段を降りると船倉は天井の高さが3?近くあり、まわりの鉄板の壁に沿って、一段に仕切られ、その上下と床が8百人余りの疎開学童と引率の先生の寝床となりました。
船はいつの間にか動きだしており(記録では乗船17時、18時35分出港)、船倉では大勢の学童に対して手渡しで救命胴衣が配布され、装着方法の説明がなされました。また、いつ使うようになるかも知れないので常時着けておくようにとも指導されました。
その夜は暑いのと群衆心理でなかなか寝つかれず、5、6年生の男子生徒は渡された救命胴衣も着けずにふざけて騒いでいましたが、女子生徒は教えられたとおり救命胴衣を着け、枕を並べてたわいのないおしゃべりをしていました。
私の隣には又従姉妹の糸数規子さん(5年生)がいました。また、向かいに一升ビンに入った水を持った同級生の外問さんがいて私が水筒を忘れてれてのどが乾いていることを告げると少し飲ませてくれました。
翌22日は台風が近づいているとかで船は大変揺れていました。夕方、敵の魚雷に備えて演習というので、ベルの合図でみんな甲板に集まって船長さんのお話を聞きました。その晩は特別に蒸し書く、胸と背にランドセルを背負ったような暑苦しい救命胴衣は外したかったのですが、教わったとおり我慢して着けたまま寝ました。
寝入ってほんのしばらくすると「ドカーン」不気味な音とものすごい振動に目が覚めました。(記録では22時12分)
魚雷だ!船倉内は、一寸先も見えない暗やみ。「先生!」「お母さん」「助けて!」今まで静かだった船倉は一瞬のうちに修羅場に変わっていました。
隣に寝ていた則子をゆさぶり起こし、手をつないではし子段の方へ、そしてはし子を途中まで登ったとき、「ドカーン」と2度目の振動で振り落とされてしまいました。則子とはそのときが最後で再び会うことができませんでした。
足元には、もう海水が人っていました。上の方では誰か盛んに懐中電灯を振り回して「出口はここだ! 出口はここだ!」と大声をはりあげ叫んでいました。
やっとの思いで甲板にはい上がつたとたんに「恐ろしい」という実感が出てきました。というのは、乗船したときの海面の位置はずっと、下でしたが、今は足元近くにあり、眼前には濁流が今にも船を飲み込まんばかりに大きなうねりとなってもり上がってきていたのでした。
船は立つこともできないくらい傾いていました。船員が「飛び込め! 飛び込め! あと10分で船は沈むぞ」と怒鳴っていました。私は泳げないので飛び込むこともできずにただぼうぜんとデッキの柱につかまってもう死ぬんだなあということを考えて立ちすくんでいました。
対馬丸の航跡と沈没位置