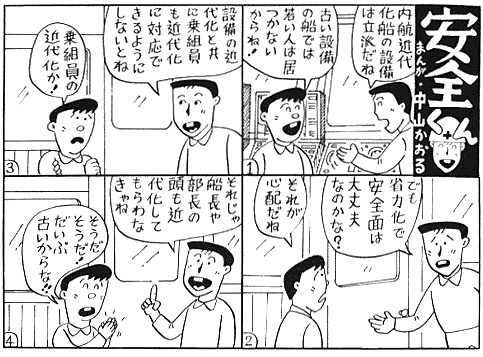本船乗員の効果的なサポートが得られないならば、新しい操船システムになじみの少ないパイロットは使いこなすのが困難になる。その結果として安全のレベルは彼の五感に頼る域を出ないことになる。座礁した後でやっと危険に気づくような事故を繰り返してはならない。
従って、搭載した機器のレベルに応じた船上の任務分川が明確化される必要があるし、すでに先進的なバース等で実施されているようなパイロット支援システムも検討すべき時代である。
このように考えると、船の設備も考慮したヒューマンリソースの管理の重要性も明らかであろう。設備の可能を熟知して操船するにはシミュレータ訓練が望まれるが、日本ではこの普及すらまだ検討中である。
翔陽丸の場合にもARPAの経験すら乏しい内航船員にとって統合操船システムは近寄りにくいシステムであり、使っていただくにはメーカーの技術者が相当期間乗船して説明する必要があった。垂船前にシミュレータ訓練が望まれるというのは実証試験の大切な結倫である。
おわりに
現在、ISMコードの適用を控えている時期に当たるが、ここでいう安全管理とは船と操船者が一体となって安全な運航が達成できるように品質管理されるということである。
とくに困難な海域では必要な支援システムを搭載し、合理的な操船計画確立、周知させ、その下での任務分担を明確化し、効果的なチームを構成する必要がある。それを点検、履行させるのがポートステートコントロールの役割ということになる。
新しい操船システムヘの人間の適応を促進するには必要に応じてシミュレータ訓練も求められよう。船と人の一体としての科学的管理の時代の到来である。
時を同じくして、日本でも統合操船システムヘの移行期の到来を迎えている。
船員のワイングラス型年齢構成を考慮すると、今日の運航技術を使いこなす形での安全運航体制が課題になるだろう。
内航船での新しい試みは日本の海事社会全体の課題でもある。転換の時期をすみやかにうまく乗り切りたいものである。