図4 今日の安全支援の考え方
(人間に適切な情報を提供して正しい判断を促すとともに、
それでも生じるかも知れない不安全事象に対して、
警告して是正を促す)
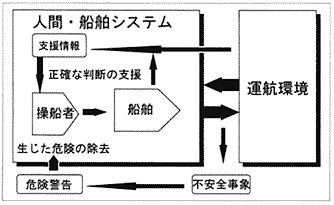
しかし、DGPSだけで船位を与えても、具体的に浅瀬との関連が分かりやすく示されなければ操船者が使いこなせない。
また、チャートプロッタという形でチャートテーブル上に船位表示する場合、本船の位置と水深との関連をモニターすることは可能であるが、配置上から視界情報を得ながらの利用は困難で専従のオペレ一夕が必要となる。
結局、視界も見ながら、海図上で座礁の危険も監視するには、操船者の前面に置かれたCRT上に情報を利用しやすい形で表示することが必要になる。
衝突の防止に関しても航行船舶の動勢を把握するレーダー情報を使いやすく加工して身近に表示するとともに、見過ごした危険を警告する機能を必要とする。
このような安全支援の考え方を図4に示す。まず、操船者に適切な情報を提供して正しい判断を促すことである。続いて、それでも生じるかも知れないミスは警告機能が是正を促すようにすると、この警告を無視して事故に至る可能性は相当に小さくなると期待される。
操船者に注意深い操船判断を求めることは重要であるが、それに頼らず、積極的に判断しやすい情報を提供するとか危険を警告するとかで、安全のレベルを飛躍的に高めるのが今日の安全対策の考え方である。京葉シーバース等で採用された離着桟支援はこのような見地から開発、導入されている。
また、浦賀水道でのタンカー座礁事故後の安全対策として、日本郵船(株)ではここで申しあげたような設備を搭載される運びとなっているが、近い将来には船社全体に普及すると期待される。
従来、このような安全性を確保するための機能は船上の人間のチームとしての機能で確保されてきた。しかし今日では混乗化が進むとともに操船者の環境も大幅に変わり、陸上勤務が長い場合も多く、見かけは同じ資格の船員が確保されているとはいえ、実質は相当に変化している。
統合操船システムは操船において人間が果たしてきた役割の相当部分を担い、人間でなければならない部分を操船者の役割として、両者の間を効果的にインターフェイスで結ぶ試みである。
このようなシステムは機能に熟知して使いこなすと抜群の効果をあげるが、馴れないとかえって危険な場合もある。欧州での経験ではその船固有の設備に馴れないパイロットが使いこなしにくいことが問題になっている。
このような場合、設備の標準化と訓練が基本的に重要になるが、それとともにシステムの操作は本船の乗員が補佐する形でパイロットの効果的な連携を実現することが重要になり、その意味でのチームプレーの重要性は変わらない。
効果的なチームプレーを実現するには操船計画が全員によく理解されており、任務の分掌が明確化されていることを要する。
内海水先人会はディスクトップシミュレータを用いて操船設計をブラシュアップしている。番の州や京葉シーバースでは十分な検討を経た標準操船計画が採用され、事前に周知されることになっている。