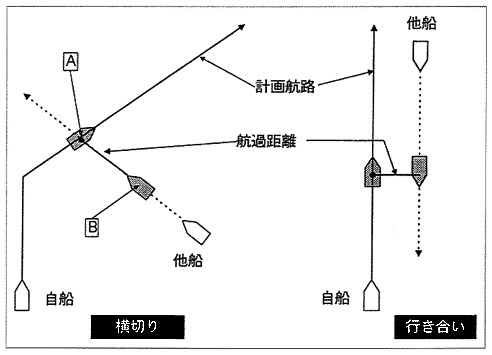この場合、単純明快な結果で考える必要があり、予定コースライン上を航行した場合の遭遇船舶との航過距離を表示することが有益である。図3はこの方法を示す。自船と接近する航行船の航過距離を見ながら、自船の予定コースラインの安全性を確認できる。
この新しい避航支援システムは現在の針路をべ-スにしたARPAを、航行予定コースラインに沿って航行する場合に対応できるように機能拡張したもので、最初の試みである。こうした衝突・座礁防止の支援法は操船シミュレータ上で有効性を確認しているが、実海域での実績は今回の実証事業の大きな柱となる。
統合操船システムと安全運航
浦賀水道で生じたダイヤモンドグレースの座礁事故は安全性の重要性を再認識させるものであった。衝突と違い、座礁は付近の水深が分かり、本船の位置と航行}定が確認されていれば容易に避けられるはずである。
しかし、操船者が見る海面からは水深、しかも通過する位置の水深は分からないから、海図上か陸上物標との関係で与えられる判断基準で確実に確認しなければ、「うっかり」ミスをおかす可能性は人である以上は避けられない。
統合操船システムの場合、自船の喫水に応じて可航領域を決めて色表示しておくと、自船の現在や近い侍米の位置がCRT上に重ねて表示されるので一目りよう然と座礁の危険が分かり、うっかりミスの可能性は随分と少なくなる。それでも残るうっかりはシステムの側から警告させるようにすると、警告を無視してまで座礁する艀例はほとんど生じないと期待される。
船位はGPSで容易に計測でき、近い将来海上保安庁のサービスが始まるDGPSでは数メートルの精度で分かるから、電子海図と組み合わせると座礁防止支援は技術的には何の問題もない。
図3 航過距離の表示法