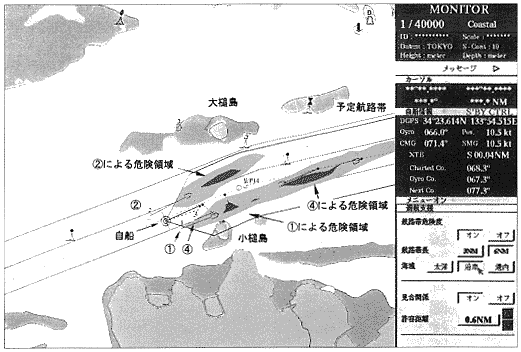このような情報が提供されると、目視でベアリング角を見続けるのと違い、はるかに容易にしかも多数の航行船に対する近い将来の航過関係を知ることができるから、衝突の危険の判断が熟練によらず統合操船システムを搭載した翔陽丸の操舵室とも容易になる。そこで、若い船員ほどARPAを頼りに操船する傾向がある。
図1 衝突防止を支援する予定航路帯での危険度表示
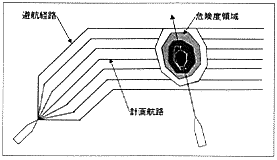
しかし、このARPAの限界は一旦変針を開始すると、その後の見合い関係についての情報が分からないことである。船位誘導を行う時に今はこのコースライン上を航行しているが、どこから次のコースラインに変更するという形で、変針も含むある程度の長さの予定コースライン上での衝突・座礁防止の判断に対する支援の導入が望まれる。つまり、変針したり、変速した後の見合い関係の評価が与えられれば予定コースラインの選択が容易になる。
この目的のために、日本の海上交通工学的研究の成果を活用して、2つの支援方法を開発した。
(1)予定航路帯における衝突と座礁の危険度表示
図1に示すように、自船が航行する予定のコースラインの周りに左右に避航した場合を想定し、この航路帯上の各位置での衝突の危険を表示する方法である。この危険の評価に長澤教授(海上保安大学校)の提案している避航空間閉塞度という指標を用いることにすると、他の航行船舶との関連で自船の行動の自由度が失われないようにコースラインを選ぶことができる。
つまり、図2に例を示すように衝突の危険は予定航路帯上に色表示されるから、赤や黄色に塗られた領域を避けるように折れ線の形で予定航路を指定し、承認を与えると自動船位誘導機能で避航できることになる。
(2)予定航路上での障害物からの航過距離表示
前述の方法で自船の安全なコー スラインを選んだ場合にも、どの船からどの程度の安全距離を確保し得ているかが明確でないと、安心して最終判断できない。
図2 避航支援機能による表示例(衝突の危険度と航過距離が海図上に表示されている)