また航機両用の航海士教育は、6年前に1部でそのための教育をしたが今は実施していないという。
その理由は(1)英国の船員教育費用の多くは船会社が負担しており会社からのニーズがない。(2)現在の自動化の程度では航海・機関両方を担当することは困難である。(3)英国では自動化の行方がまだ定まっていない……からだという。
ワーサッシュ海亊センターも航海コース1クラス(1学年で60人)機関コース(1学年で15人)の教育を訓練センターと合わせて教育している。
また最近の標準的な乗組員体制は次のとおりである。
船長、1等航海士、2等航海士、3等航海士各1、航海/機関両用部部員6、機関長、1等機関士、2等機関士、3等機関士各1、調理2、司厨1、合計17人。
英国における船員教育の最大の特色は経験主義である。最近のプログラムの座学と乗船実習の割合はつぎのとおりとなっている。
甲板実習4年間
陸上における講義および実習71週(40%)、社船実習119週(60%)
機関実習生3年間
陸上における講義および実習68週(70%)、社船実習18週(30%)
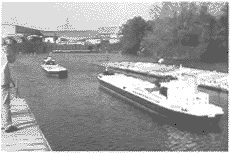
マンドモデルによる訓練風景
あとがき
ロンドンまでは約1時間半と近いが、のどかな牧場のある住宅街に滞在した。
イギリス人は個人主義というかあまり他人のことに干渉しない。紳士的で、ユーモアや時には皮肉を忘れない。進歩的な考えがあるかと思うと保守的である。つまり個人個人がしっかりした自分の考えを持っているということだろう。
わずか15日間の滞在だったがワーサッシュ海亊センターやホテル、カントリークラブの人達とも親しくなることができ、誰がどのような人かが分かるようになった。
また、英国の英語は教科書英語で、筆者にとってはスウェーデン、ドイツ、オランダで聞いた英語より格段分かりやすかった。
(次回はアメリカ)
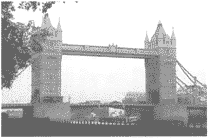
タワーブリッジ
新刊紹介
海洋気象のABC 福谷 恒男著
近年、気象情報の伝達方法などには、飛躍的な発展があった。また、気象予報士制度の創設等もあり、天気予報の世界もかなり変わってきた。
しかし、通信や計測の手段が高度に発達しても、気象・海象が船舶の運航に及ぼす影響は本質的には変わらない。
本書は、入手した気象情報をよく理解してその利用価値を高めるための基礎知識が十分身につけられるよう、章ごとに詳しく気象に関する事柄を解説している。
今回の3訂版でも、海象をはじめとした説明を補いつつ、気象観測と気象予測の基礎を学ぶ人にわかりやすくという当初の姿勢が保たれている。
気象に関心を持つ多くの人たちに一読を勧めたい書である。
(成山堂書店・1,000円)