見学のできる灯台(2)
野島埼灯台
(社)燈光会
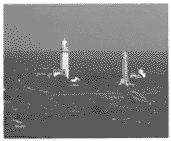
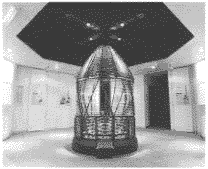
野島崎灯台全景 きらりん館に展示された2等不動レンズ
野島埼灯台は、千葉県房総半島の最南端の岬に立つ8角形の美しい大型灯台です。眼下に国定公園の秀景が広がり、広大な太平洋からこの灯台を目指し東京湾に入る大型船の列が遠望されます。
灯台にはレーマークビーコンが併設され、船舶気象通報業務も行っています。
この2月には「きらりん館」と命名された灯台資料展示室が開設され、子供たちにも人気を集めています。
南房総は東京アクアラインの開通もあって、フラワーラインと灯台を訪れる人で賑わっています。
灯台の生い立ち
野島埼灯台は、開国の歴史を飾る慶応2年(1866)にアメリア、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだ「江戸条約」によって建設を約束された8つの灯台の1つです。
当時、日本列島周辺海域は、航海に条件の厳しい暗岩礁等が牙をむくダークシーでした。このような危険な海に三浦半島の観音崎と房総半島先端の野島崎に、初めて大きな近代の灯が相次いでともされたのです。
江戸条約を受け継いだ明治政府は、英国人技師RHブラントンにより、多くの灯台を建設していますが、野島埼灯台を含む東京湾周辺の4灯台だけが、フランス人技師、FLヴェルニーの手によっているのです。
当時徳川幕府は、海軍増強のため横須賀製鉄所(後の造船所)の建設をフランスの指導で進め、江戸湾出入りのための灯台建設を急務としていました。この事業を引き継いだ明治政府は横須賀製鉄所雇いの首長フランソア・レオン・ヴェルニーにより発足早々これらの灯台建設を進めたためです。
灯台の変遷
野島埼灯台は、明治の初め洋式灯台の誕生にあたって、対岸の観音崎と並んで真っ先に選ばれたように、海上交通の大変重要な位置にあります。太平洋から最初の目標でもあり、今日、東京湾に出入りする船や沖合を通過する船舶は、必ずこの灯台によって自船の位置を確認し、進路を決定して安全で効率的な航海を行っています。
野島埼灯台は、海上交通上、観音埼の明治2年1月1日の点灯に呼応し、同1月10日、木造4角櫓型の仮灯台で点灯させ、2月14日には本灯台の工事にかかり、同年12月18日に完成しました。
当時の灯台は、白色8角形のレンガ造りで基礎から灯火まで30メートル、フランス製の第1等フレネルレンズと石油灯器の6,500燭光でした。残念ながら関東大震災で、地上6メートルで折損、大音響とともに倒壊しました。
現在の鉄筋コンクリートの灯台は復旧工事によったものです。その後電化され、120万燭光の光りを放っています。
灯ろうは、太平洋戦争で無数の機銃を受けましたが、昭和21年に復旧しています。
灯台へのアクセス
JR=東京から1時間45分館山からバス40分
車=アクアライン経由白浜まで2時間45分