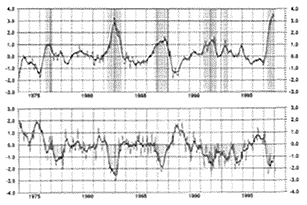エルニーニョ現象の監視
エルニーニョ現象が発生すると地球規模で大気の流れが変化して、世界の各地に異常高温や低温、洪水や干ばつなどの異常気象をもたらし、社会や経済に大きな影響を与えます。
日本でも冷夏や暖冬、梅雨明けの遅れなどが統計的に起きやすいと指摘されています。そのため、気象庁のエルニーニョ監視予報センターで全世界から収集したデータを使って、太平洋赤道域の海面水温分布、海洋内部の水温分布など海洋の状況と大気の状況を監視しています。海洋の監視には海洋データ同化システムを用います。これは断片的で数も少ない海洋の観測データと海洋大循環数値モデルとを組み合わせて、海洋内部の水温の分布状態を推測することができるシステムです。監視の結果は毎月刊行物で発表しています。
今回のエルニーニョ現象の推移
1995年から96年にかけての太平洋赤道域の海面水温分布は西部で平年より高く東部で平年並みから低い状態が長期間継続しました。西部では暖かい水が蓄積され、海面から深さ数100メートルまでの海洋表層の水温にも大きな正偏差が持続しました。
96年の年末と97年3月に西部赤道域では海面上を強い西風が吹いて、形成されていた暖水域が東に広がりはじめ、5月にはその東端が南アメリカ沿岸に到達しました。その後11月まで海洋内部では東部赤道域で正偏差が増加し続けました。
一方、西部では9月ころから負偏差となり、98年1月には西経110度付近まで広がりました。
この海洋内部の変化にともない監視海域の海面水温偏差は1996年12月にマイナス0.8℃の極少値となった後上昇に転じ、3月以降は正偏差になりました。とくに5月から8月にかけては急速に増大して8月には+3.1℃となり、その後も10月+3.3℃、11月+3.6℃、12月+3.4℃、98年1月+3.0℃と大きな正偏差を示しました(図2参照)。11月の3.6℃は解析データが整っている1949年以降の最大値です。最新データとして図3に1998年1月の海面水温分布を示します。西経160度以東で2℃以上平年より高く、西経105度から西経90度にかけての一部の海域では4℃以上高くなっています。一方、西部の東経170度以西には負偏差域が広がっています。
〈図2〉エルニーニョ監視海域(上)における月平均海面水温
偏差(中)および南方振動指数(下)の時間変化
海面水温偏差の単位は℃で、期間は1973年から1998年1月までです。
平年値は1961年から1990年の30年平均値です。中段の陰影はエル
ニーニョ現象の期間を、下段の陰影はSOIのマイナス側を示しています。
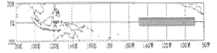
エルニーニョ監視海域(北緯4度〜南緯4度)(西経150度〜西経90度)