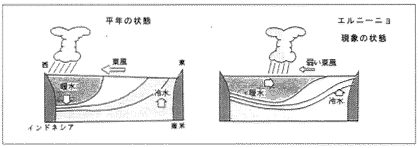海の気象/エルニーニョ現象97/98
中村和信
(エルニーニョ監視予報センター)
はじめに
1997年の春にエルニーニョ現象が発生し、1998年2月現在も継続しています。その間に世界各地でその影響とみられる異常気象が発生し関心を集めています。
ここでは、エルニーニョ現象の発生期からの推移などを説明します。
エルニーニョ現象
エルニーニョ現象というのは、太平洋赤道域の日付変更線からペルー沖にかけての海面水温が、2〜7年おきに平年より1〜2℃、ときには2〜5℃も高くなり1年から1年半程度続く現象です。
図1は発生の仕組みを説明したものです。太平洋赤道域では通常東から吹く貿易風によって表面付近の暖かい水が西側に吹き寄せられ、東側ではそれを補うように下から冷たい水がわき上っています。そのためペルー沖に比べてインドネシア付近では海面水温が高く、対流活動も活発になり海面気圧が低くなります。逆にペルー沖では海面気圧が高くなるため、太平洋の赤道域では海面付近で貿易風と呼ばれる東風が維持されています(図1左)。
ところが貿易風が何らかの原因で弱まると西部の暖かい水が東に移り、東部ではわき上りが抑えられて海面水温が上昇します。この時通常よりも海面水温の高い領域が東部に現れ、同時にインドネシア付近にあった対流活動の中心も東に移動して、大気の流れは弱い貿易風を維持する状態となります。これがエルニーニョ現象です(図1右)。
貿易風の強弱に関連して太平洋赤道域でみられるこのような気圧の変動現象は「南方振動」と呼ばれています。
東部と西部の海面気圧の差が、あたかもシーソーのように数年周期で振動することは以前から知られていましたが、最近、南方振動とエルニーニョ現象は、大気と海洋の一帯の現象をそれぞれの側面から見たものだと認識されるようになり、両者をまとめてエルニーニョ南方振動(ENSO)と呼ぶようになりました。
この南方振動の指標を南方振動指数といい、タヒチ島とオーストラリア北部の海面気圧の差から求めます。この値は貿易風の強さの目安となり、正のときは貿易風が強く、負のときは弱いことに対応します。
気象庁ではエルニーニョ現象の動向を把握するため監視海域(北緯4度〜南緯4度、西経150度〜西経90度)を定めてその海面水温の変化を監視していますが、図2はその監視海域での海面水温の平均偏差(その時の水温と平年の値との差を平年偏差といい、正の時は平年より高いことを表します)と南方振動指数の時間変化をあらわしており、極めて高い相関のあることがわかります。
〈図1〉エルニーニョ現象の発生の仕組み 太平洋の赤道に沿った鉛直断面の模式図。
貿易風の強弱、暖水の分布、対流活動域の位置などを示しています。