1階に通されたわれわれも荷物を片づけて横になることにした。1枚の布団を横に敷いて4人が足を互い違いにして、掛布団を引っ張りあうような状態であった。2階の奥のほうにもすでに多くの人たちが横になっていた。
山小屋に泊まっている人の多くは頂上でご来光を見るために夜半過ぎに出発する人が多い。横にはなっているもののざわざわしていて寝つけそうにもない。
山小屋の混雑ぶりは人からは聞いていたが、いざ直面してみるとその雑然ぶりには圧倒された。
時間が経つにつれて次から次へと登山者が入ってくる。だんだんすき間がなくなり、まったくいわしの缶詰なみのラッシュぶりである。商売柄とはいいながらうまく詰めてゆくものだと感心する。
また頂上へ向かう登山者の列は夜になっても続いている。京浜や阪神から夕刻登山口に着いて夜を徹して登り、翌日には家路をとるという。
最近は若い人が多くなってきたとのことである。
山小屋の中は消灯しているものの寝ついている人は少なく落ち着かない。
夜半を過ぎて午前1時になると、たくさんの人が起き出して出発の準備をはじめた。
頂上でご来光を眺めるために2時に出発する予定という人が多かった。
われわれ家族は小学2年生という次男の健康状態を考え4時半ごろ山小屋を出発した。ひっきりなしに登ってくる人の群れの中に加わって登りはじめた。
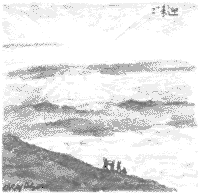
今朝も晴れているが雲が厚く、下のほうは霧がかかってよく見えない。
山小屋での一夜が雑然としていたので眠れなかったので疲労が残った。子供たちはさわやかな空気の中を元気よく登っていた。
2時間ほど歩いて道のかたわらで山小屋で買った弁当を食べた。下界にひらけた雄大な風景も、ところどころが雲海や霧にさえぎられていた。
9合目の烏帽子小屋を過ぎて急こう配の道を登っていたが、次男が少し苦しいので休憩しようと言い出した。登山道のかたわらで座って休んだ。しばらくして楽になったというのでふたたび登りはじめた。
いくらも行かないうちに次男の顔が青ざめてきた。苦しそうにしているので、近くの小屋に入って休むことにした。しばらく様子を見ていたが快方に向かう兆しは見えなかった。
山小屋の人は高山病ではないかと言っていた。4人で話し合った結果、次男の健康状態を考えて下山することにした。山小屋を出てゆっくりと下りはじめた。少し時間が経ったころから、次男のさきほどまでの苦しそうな表情も薄らぎ、次第に元気になっていった。
傾斜の急な登山道を足元に注意しながら、歩きづらい道を下った。時折霧が濃くなったり薄くなったりしている中を、多くの人たちに混じって登山口へ急いだ。
現在、長男は奈良県に、次男は大阪府吹田市にそれぞれ家庭を営んでいる。
河内長野市の実家に来ても飾り棚の一輪ざしを見ることはほとんどない。時として私には4人で富士山頂を目指した28年前のきずなが、この一輪ざしの花器を通じて、何の脈絡もなくよみがえることがある。