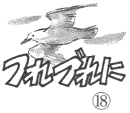 一輪ざしの花器
一輪ざしの花器
山本 繁夫
岡安 孝男画
家のつくりつけのげた箱の上に飾り棚があり、その一隅に黒い陶器の一輪ざしが置いてある。横面に「昭和44年7月27日富士山登山十国峠展望記念」と焼き込まれている。そのおりの小さなパーティー、私と妻と長男、次男の4人の名前も書き込まれてある。
この一輪ざしは、富士登山から下山後、大阪への途次に十国峠に立ち寄った時のものである。十国峠の展望台広場の一角に釜があり、素焼きで売っていた一輪ざしを買い記念の文字を書き入れた。その時に長男、次男が山や雲、また家などを描き、色づけしてうわぐすりをかけて焼いてもらった。約30年ほど前のことである。
そのころ、子供の成長とともに富士山登山が家の話題の中に登場するようになってきて、話が具体化したのは昭和44年の春で、次男が小学校の2年生になったころである。
今までには近鉄や南海電鉄主催のハイキングなどに参加する程度だったので、張り切っていた。
高校1年の長男はボーイスカウトの団員として大阪周辺の山歩きをしたりしているので、いくらか山には馴れていた。次男も大丈夫だろうということで富士山への山行計画書を私が作り、実行することとなった。
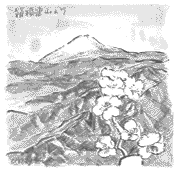
当時、乗船中だった私はその年の7月初旬に休暇下船し、念願の富士登山のための準備にあたった。
7月26日朝、私と妻、長男と次男の4人は新大阪駅東京行きの新幹線こだまに乗った。途中三島駅で降りて河口湖行きのバスに乗り換え、富士吉田5合目登山口に着いたのが午後4時を過ぎていた。
5合目の雲海荘の前を通り、火山独特の地形の中につくられた道を登って何人かに追い抜かれたり追い越しながら少しづつ登って行く。家族の中で1番重いキスリングを背負った長男は、次男といっしょにかなり前を歩いていた。
多くの登山者にまぎれて見えなくなったりしたが、時折追いつくのを待っていることもあった。
この時期の富士登山といえば最盛期で、登山者が最も多数集まるシーズンである。出会う人もバラエティーに富んでいて外人の姿も多い。さすが日本列島の中で1番高い山だけのことはある。
草木のない火山帯特有の砂れきの道をゆっくり登って行く。6合目のいくつかある山小屋の前を通りすぎ7合目近くの岩場にはくさりが取り付けられたところがあり、登りの順番を待つための行列ができていた。
このあたりまで来ると少し疲れが出てきた。子供たちは相変わらず私よりかなり前を歩いていた。なんとか少しでも追いつこうと思うがなかなか追いつけない。
5合目登山口を出発してから約3時間近く歩いて、午後7時すぎに8合目の東洋館という山小屋に着き、そこで泊まることにした。
次々と登山者が入ってくるので小屋の中も混雑してきた。持参してきた弁当を食べ終わらないうちに、山小屋の人が布団を敷きはじめた。