調査項目および内容
(1) 海上交通安全法「行先の表示」
操船者に対する意識調査を実施して、現行の行先信号(全航路)に関する問題点を把握するとともに、既存の行先信号の改善や新しい信号方法に関する調査結果を検討し、航路航行中の信号の掲揚作業や揚げ換え作業が不要となる改善策を提言した。
(2) 来島海峡の航行安全対策
来島海峡のような複雑な航行環境にあっては、船、人、環境をひとつのシステムとして評価・検討する必要があるとの観点から理論的なアプローチを試みた。
a 評価指標の策定
来島海峡の航行特性を評価するために、操船特性として環境ストレス値、SNS値、操縦特性として斜航角、追越し特性、測位特性として測位誤差、通特性として推定困難度の多面的な評価指標を策定した。
b 航法の比較および安全対策(案)の検討
順中逆西および右側通航の両航法による大型船と小型船の操船シミュレータ実験を実施し、その結果に評価指標を適用して、各航法における問題点等を整理するとともに、それぞれの対応策(案)を示した。
沿岸域環境保全リスク情報マップ整備の促進
目的
「沿岸域環境保全リスク情報マップ」とは、海上において大規模油流出事故が発生した際に、沿岸域において油汚染の被害を受けやすい地点等をあらかじめ予想し、地図上表示した資料(情報図)である。
これは、自治体等関係者が、あらかじめ油防除体制を構築し油防除計画を策定するとともに、万一事故が発生した場合、オイルフェンス等防除資機材の具体的配備や油の除去等の作業を迅速かつ的確に行えるようにするための、基礎資料となりうるものである。
国際的にも、その重要性が強く認識されており(OPRC条約=1990年採択)、当協会においても1993年(平成5年)に新たな情報図を作成するための指針を取りまとめるとともに、平成7年度は東京湾、平成8年度は伊勢湾、そして平成9年度は大阪湾を対象に試作図を作成した。
調査項目および内容
情報図上には、油流出事故時の海岸清掃作業の難易度等に応じて、海岸線の種類がおおむね8種類(閉鎖性人工護岸、粗粒子の砂浜等)に分類表示されるとともに沿岸域に存在する油による汚染に対して脆弱(ぜいじゃく)な指標(野生動物の分布状況、発電所の取水口の位置等)が記号またはシンボルマークで表示されている。
またデータブックには、これらに対するより詳細なデータおよび関係行政機関等の連絡先等が記載されている。
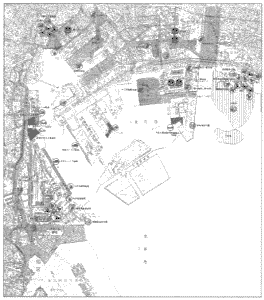
沿岸域環境保全リスク情報マップの一例
(東京港の1部)