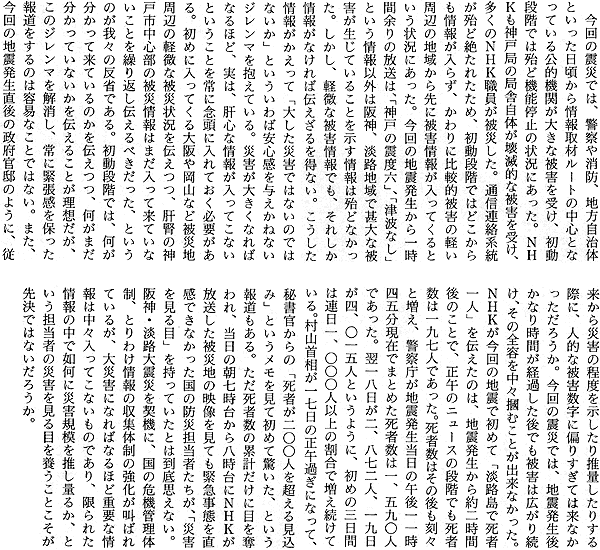午前六時を過ぎると、各地の震度のほか、徐々に映像や雑感が入り始めた。地震が起きる直前にさかのぼって大阪局や京都局内の様子を撮影したスキップバックレコーダーや大阪局近くのコンビニエンスストアーの店内の様子、地下鉄駅構内の停電などの映像が次々と全中(全国向け)で放送された。午前六時台には神戸局の宿泊勤務の記者の報告など神戸市内から三回の電話リポートを放送しているが、中でも、六時四〇分頃にアナウンサーが神戸市中央区の高台の家から伝えたリポートは大震災の一端を伝える第一報であった。「私は神戸市中央区籠池通りの神戸市内を一望できる高台にある八階建てのマンションの四階にいます。大阪方面に四か所、神戸市三宮の東側に三か所火の手が上がっているのがはっきり見えます」というリポートは、神戸で容易ならぬ事態が起きていることをうかがわせるものであった。ただ一つ残念なのは、この情報は極めて重要なものでありながら、映像を伴っていなかったために、一般には殆ど注目されなかったことである。
午前七時一分、あの神戸局内のスキップバックレコーダーの映像が初めて全中のテレビで放送された。震度七の激しい揺れによって鉄筋コンクリート造り四階建ての局舎が翻弄され、放送部室内のスチール製の机や棚が前後左右に大きく揺さぶられ、宿泊勤務の記者が落下物を避けるように簡易ベッドの毛布にくるまるさまがつぶさに映し出された。震度七の状況を初めてテレビカメラがとらえた映像は海外にもいち早く伝えられ、神戸の市街地は地震によって大変な事態が発生していることを予測させる極めて貴重なものであった。この放送以降、神戸市内の建物の倒壊の様子や、火災の生々しい映像が伝えられ、さらに神戸局前からの中継放送は、神戸市内の異常事態をはっきりと裏付けるものであった。そして、八時一四分、NHKが他社に先駆けてヘリコプターから中継した阪神高速道路の倒壊現場や、火災が各所で発生している映像は、この地震が阪神地域に未曾有の大惨事をもたらしていることを示していた。
「NHKに残された課題」
この間の視聴率を見ると(ビデオリサーチ調べ)、関西地域では、午前五時四九分の地震発生直後は六・七%であったが、五時五一分には三三・〇%、六時二五分には三六・二%に達した。さらに、スキップバッグレコーダーの映像が初めて大阪管中で放送された午前六時五〇分から七時にかけては四三・四%に達している。まさに「グラッと来たらNHK」の言葉通りの視聴率である。
しかし、あえて自戒を込めて言えば、我々マスコミ側に「震度六」に対する慣れが生じてはいなかったろうか、という点である。「北海道浦河沖地震」(八二年)、「北海道釧路沖地震」、「北海道東方沖地震」と「三陸はるか沖地震」(九四年)というように、近年「震度六」の地震が度々発生しているが、いずれも多くの死傷者を出すことがなかった。「大したことはない」という先入観、あるいは希望的観測があって、震度階には実はその上の「震度七」の激震があることを忘れてはいなかっただろうか。それに加えて、「日本海中部地震」や「北海道南西沖地震」で津波の早さやその恐ろしさをいやというほど知らされてきたため、気象庁の方針もあり「地震速報ではまず何よりも津波情報」という意識があった。「津波なし」の情報に「ひとまず安心」という傾向がマスコミ側にあったことも否めない事実である。
「被災情報のジレンマ」