17) IIRフィルタを用いた船舶操縦性指数のオンライン推定について
井関俊夫、大津皓平(東京商船大)
IIRフィルタを用いたシステム同定の直接法を一次系近似の操縦運動方程式に適用し、実船実験データを用いて操縦性指数のオンライン推定を行なった。その結果、以下のことがわかった。1]IIRフィルタを用いた直接法は、サンプリング周期の影響をほとんど受けず、推定された結果通常のZ試験解析法と良く一致している。2]IIRフィルタを用いた直接法は、微分方程式の係数が陽に現われた離散モデルを用いているとともに、時定数設定の有効範囲が広いのでシステム・パラメータの有効なオンライン同定法といえる。
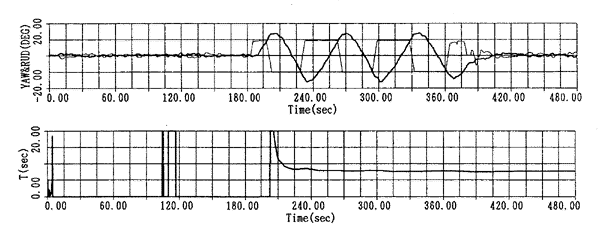
操縦性指数のオンライン同定結果
18) 小型全没式水中翼船の運動性能について
寺尾裕(東海大学)
小型全没式水中翼船かもめ50二世は1994年に進水したソーラーボートで480Wのソーラーセル、12V5AHのバッテリー4個をもち、出力500WのDCモータ台で浮上走行に成功した。この艇の横運動は、ドライバーが体重移動により制御する新しい操作系を持つ。この艇の縦および横運動を解析するために、数値シミュレーションをおこなった。その結果縦運動では運動の収束性があることがわかった。また横運動では、体重移動制御を記述する運動方程式を採用、人の制御モデルを取り入れて計算をおこなった。その結果、実船と同様に艇の横運動制御が可能となることがわかった。
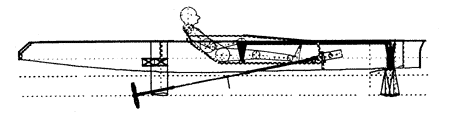
かもめ50二世側面図
19) ハイブリッド式舶用減揺装置の開発と実海域試験
月岡哲(JAMSTEC)、佐伯愛一郎(IHI)、宮部宏彰(IHI)、藤田俊助(JAMSTEC)
海洋地球研究船「みらい」は荒天でも船体の横揺れを制御し、観測作業が行えるようにハイブリッド式舶用減揺装置を開発し搭載した。船体に取付けた可動マスを振り子のように作用させ動揺は制御できるが、さらに可動マスをアクチュエータで駆動し動揺抑制効果の周波数帯域を広げ、波高4mまでの海象で横揺れ角が半減することを目的とした。シミュレーションでパラメータの変化範囲を確かめ、実海域試験(下図)で目的どおり横揺れ角をほぼ半減することを確認できた。
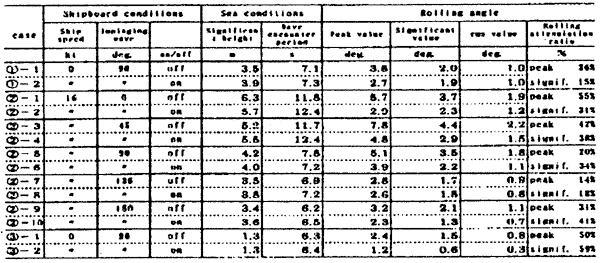
実海域試験結果
20) 重力流の先端部の構造
馬場信弘(大阪府大)、岡村将治(大阪府大大学院)、福庭哲也(大阪府大大学院)
水門開放によって生じる重力流の実験と計算を行い、先端部の構造について調べた。開放する流体の初期の厚さと水門の位置を変えて、染料とシャドウグラフ法を用いた可視化実験を行い、先端部の進行速度を計測した結果、ボックスモデルの有効性が確かめられた。またナビエ・ストークス方程式を有限体積法によって解き、発達段階の異なる重力流の先端部の構造について調べた結果、計算でも重力流の発達段階の遷移が再現され、密度場から求めた先端速度は実験結果とよく一致した。これらの結果から、重力流の先端部の形状と内部構造はその発達段階に応じて変化することがわかった。
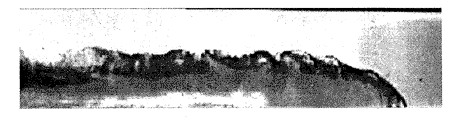
重力流のシャドウグラフ
前ページ 目次へ 次ページ