44) スラミングに対するクロスデッキパネルの弾性応答について
遠山泰美(三井造船)
構造物の弾性変形を伴う2次元水面衝撃問題を、解析的に求めた平板まわりの速度ポテンシャルの重ねあわせにより解析する手法を提案した。平坦なクロスデッキと放物線形状の波頂との衝撃問題に適用した結果、衝撃開始位置での携みと曲げモーメントは落下速度の増大に伴い、動的応答倍率の減少のため、速度の2乗比例から1乗比例に移行することが分かった。またエネルギー的考察から最大撓みの推定式を導いた。
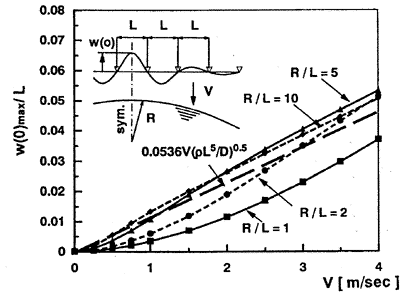
スパン中央最大撓みと落下速度の関係
45) 未知環境外乱中における弾性応答―剛体運動連成系の学習軌道制御
戚涛、鈴木孝之(東大)、渡辺啓介(東海大)、岡徳昭、榎本一夫(東大)
未知外乱を学習する制御手法を多自由度の弾性応答―剛体運動連成系まで拡張し、未知準定常外乱の下で構造応答を能動的に制御しつつ、弾性構造物を予め決められた軌道に沿って運動させ、高い精度でドッキングさせる学習制御手法の開発を行った。
学習制御手法については、収束条件を求め、数値シミュレーションにより手法の基本特性を確認し、本手法が十分ロバストであり、実用性が高いことを示した。さらに、2基の海洋構造物の模型とアクチュエータ・センサよりなる実験システムを構築し、水槽で自動設置・組立実験を行い、手法の有効性を示すとともに、柔軟な海洋構造物の自動設置・組立技術の実用化への可能性と展望を示した。
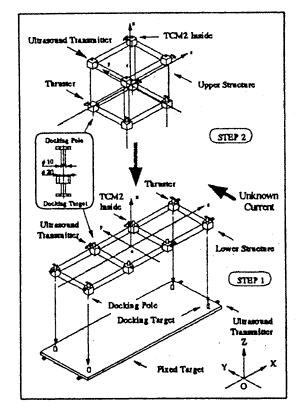
46) ナホトカ号事故時の波浪外力について
渡辺巖(船研)、大坪英臣(東大)
1997年1月に日本海で発生したロシア船「ナホトカ号」の事故原因調査が運輸省で行われた。調査の過程では、事故当時ナホトカ号がどのような荷重状況下にあったか、船体の構造強度が大きな課題であった。著者等はこの事故調査委員会のメンバーとして荷重についての検討を担当した。そこで検討されたのは、貨物の積みつけによる静的荷重成分、波浪による動的変動荷重成分等である。この論文ではこれらについてどのようにして荷重推定がなされたかを述べる。特に積み付けがサギングモーメントを大きくするものであったことを示す。波浪外力については当時の波浪状況を沖合いブイの計測値等をもとに有義波高8mの不規則波浪と推定し、その時の波浪荷重を非線型シミュレーションプログラムにより計算した。その結果、下の図に示すような船長方向の荷重分布の最大値が求められた。折損事故は衰耗等によりこれに耐える強度が失われていたため発生したことを述べている。
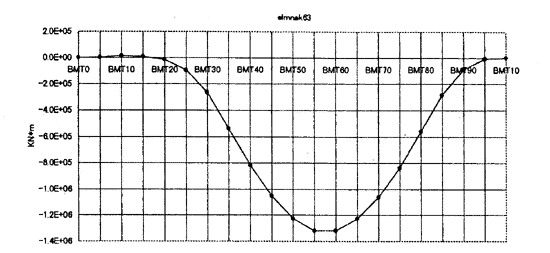
Instantaneous Distribution of the Bending moment at its maximum
47) ナホトカ号事故時の構造強度の推定
矢尾哲也(広大)、角洋一(横浜国大)、竹本博安(船研)、熊野厚(NK)、末岡英利(三菱)、大坪英臣(東大)
ナホトカ号の腐食衰耗量の推定と実験で求めた材料の特性をベースに船体はりの座屈・塑性崩壊強度を定めた。また、現地調査をもとに船底部破断シナリオを推定し、船底部破断のメカニズムを検討した。その結果、本船の折損は第一義的に腐食衰耗に起因する甲板の座屈・塑性崩壊によることが明らかとなった。
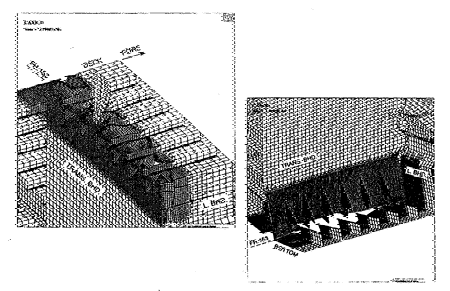
折損の大規模数値シミュレーション
前ページ 目次へ 次ページ